
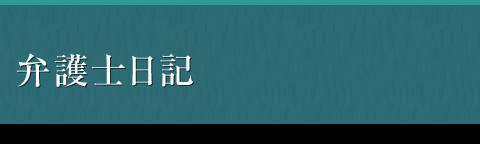
近時、外国人労働者の姿が増加している。例えば、コンビニの受付や、工事現場などで作業に従事する姿が目につく。2025年9月21日付けの産経新聞には「外国人なしでも社会は回る」という見出しの記事が掲載されていた。筆者は人口減少問題の第一人者である河合雅司氏である。今回、私は、河合氏の記事を精読した。
今年、総務省が公表した統計調査結果(2025年1月1日現在)によれば、外国人住民は、前年と比べ35万4089人の増加であり(前年比 10.7%の増加)、計367万7463人となった。日本の総人口に占める割合は3.0%となった。これは決して少ない数字ではない。
このように外国人が急増した原因は、企業が外国人を必要としているためである。なぜ必要かと言えば、厚生労働省の統計数字(2024年外国人雇用実態調査)によれば、断然多いのが、労働力不足の解消・緩和のためである。このような統計数字を踏まえ、「日本社会は外国人抜きでは回らないという意見」が多く見られるようになっている。河合氏はこの安易な意見に疑問を呈している。私見も同様である。
新聞に記載された河合氏の見解を要約すると、次のようになるのではなかろうか(ただし、例示は私見にすぎない)。
第1に、今後、日本社会は人口が急激に減少する。そうすると、内需つまり仕事の総量が減る。結果、例えば、住宅建設の戸数が現在よりも1割減少すれば、工事に必要な現場作業員も1割分少なくて済むようになる。
第2に、今後、AI技術が格段に進歩すると、ホワイトカラー(事務職。いわゆる会社員)の多くが不要となる。大量の余剰人員が生まれる。例えば、県庁で事務に従事している事務系職員は、その大半が、机の上に置かれたパソコンのキーを叩いて文書を作成する仕事を行っている。ひと昔前は、紙にペンで書いていたのであり、能率は非常に悪かった。それが、現時点では、はるかに能率が改善している(生産性が向上している)。今後、AI技術が更に飛躍的に進歩すると見込まれるため、現在の業務量を、現在の半分の数の職員でこなすことが可能となろう。そうすると、専門的技能を有しない事務系職員の半分は不要(余剰人員)となる。当然、解雇されれば収入はゼロとなる。
第3に、いわゆるエッセンシャルワーカーと呼ばれる職種は、いくらAI技術が進歩しても、人間が担う必要があり、雇用需要は減少しないと予想される。いわゆる現場の仕事であり、例えば、医療従事者、教員、警察官、トラックドライバー、介護職員、旅館の仲居、店の店員などがこれに該当する。農林水産業者もこれに当たろう。そのため、エッセンシャルワーカーについては、必ず一定数の雇用需要があり、よって、賃金水準も増加傾向を維持すると予想される。
このような傾向が今後も継続すると見た場合、上記の大量の事務職員(正確には職にあぶれた余剰人員)は、職を求めて雇用需要が高い分野(エッセンシャルワーカー)へ移動せざるを得ない。
ここで、河合氏は、「古いビジネスモデルを維持せんがために外国人労働者を大規模に受け入れ続けるならば、ホワイトカラーの仕事から移ってくる人々と競合することとなる」と警告する。
つまり、エッセンシャルワーカーのうち既に多くの外国人労働者が担っている職種への移動が起きた場合に、双方で仕事の奪い合いが起こるということである。結果、外国人労働者は用済みとなり、露頭に迷うことになる。失業した外国人が、治安の悪化をもたらす危険が生じる。治安の悪化は警察官の人件費の増加となって地方公共団体の経費増加を招く。必要な予算が組めない場合は、犯罪者集団の跋扈により、市民生活に対する多大の悪影響となって跳ね返る。
以上の分析を踏まえ、河合氏は、「安易に外国人に流れるのではなく、人口が減っても経済が成長するよう、国の仕組みを根底から作り直すほうがトータルで考えれば現実的なのである」と言い切る。私見も同様である。
企業は、今後、設備を更新し、また、AI技術を取り入れて、省力化、効率化に取り組むべきである。そうすれば、外国人を安価な労働力として使う必要もなくなる。
仮に中国や発展途上国からの低レベルの外国人労働者を日本が際限なく受け入れた場合、今後、10年~20年のスパンで見た場合、やがて大きな負の遺産として日本の発展を妨害する重大要因となる可能性が高い。これまで移民を受け入れてきたヨーロッパ諸国は、現在、その弊害の大きさに気づき、移民排斥を訴える政党が各国で躍進している。当たり前の社会現象であり、私見はこれに賛同する。
今後、日本政府は、単純労働力の補充のみを目的とした低レベル外国人の流入をストップし、真に日本の発展に役立つと考えられる高レベルの技能を持った外国人(例 高度のAI技術を習得した4年制大卒者)のみを受け入れるよう、法律制度を見直す必要がある。左翼思想に染まった某新聞社説のように、外国人との共生を唱えること自体が根本的に間違っているということである。

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.