
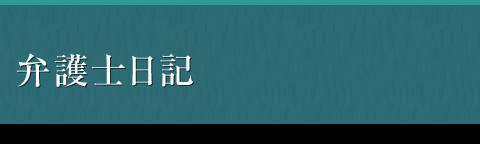
逸失利益については、前回の弁護士日記でも触れた。前回に引き続き今回も逸失利益について述べてみたい。逸失利益については、大きく二つの論点がある。第1の論点は、労働能力喪失率の問題であり、この点は、前回に述べた。
もう一つの論点は、基礎収入の認定という問題である。つまり、逸失利益を計算するには、労働能力喪失率、労働能力喪失期間及び基礎年収の3点が確定する必要がある。
例えば、ある人が事故による後遺障害のために20パーセントの労働能力を失ったとする。そして、怪我の治療が終わって症状が固定した時の年齢が47歳だったとする。そうすると47歳から67歳までの期間は20年間となる(就労可能年齢は、実務上、原則として67歳までとされている。)。20年間のライプニッツ係数は12.462である。この場合の逸失利益の計算は、[基礎年収×0.2×12.462]で算定できる。
そうすると、同じ程度の後遺障害を負い、年齢も同じ条件の被害者の場合、基礎年収の数値次第で逸失利益も大きく変動することになる。基礎年収をいくらと見るかについては、例えばサラリーマンのような場合は、源泉徴収票に記載された年収を基準として計算すればよいから、余り問題にならない。
問題になるのは、自営業者の場合である。自営業者のうち、税務署に対し毎年確定申告をしている人の場合は、原則としてその確定申告の所得を基準にすればよい。ここでいう「所得」は、売上から必要経費を控除することで出てくる。しかし、確定申告をしていても、常識的に考えて、その所得では到底生活できないような所得額の場合はどう考えるべきか。
この場合は、いわゆる過少申告が行われたということであるから、実際にあった所得を証明できれば、裁判所もその所得を基準に逸失利益を算定してくれるのが通常の取扱いである。ただし、証明する証拠が十分にそろわないような場合は、賃金センサスの年収額を基準にして適宜の所得が認定されることが多い。
例えば、大阪地裁の平成18年2月7日判決は、被害者の妻が経営していたバイク店で働いていた40歳の男性(夫)被害者について、給与額を証明する証拠がなかったにもかかわらず、賃金センサスをひとつの目安として509万円の年収があったものと認定した。
同じく、大阪地裁の平成18年2月10日判決は、170万円の所得があったと確定申告していた男性被害者(事故当時71歳)について、その金額では家族4人が生活していくことは困難であるなどという理由から、実際は385万円の年収があったものと認めた。
さらに、大阪地裁の平成18年6月16日判決は、275万円の所得があったと確定申告していた画家(症状固定時61歳)について、売上は年間600万円あったと認定した上で、その6割にあたる510万円の所得を認定した。
このように考えることができるのであるが、これには反対論もある。損保会社の方から、税務申告の際には実際の金額よりも過少申告をしておきながら、ある日突然、自分が交通事故被害者になって、その後に裁判を起こした段階で、実際の所得はもっと多かったと主張することは信義則に反することであって、おかしいという反論が出ることがある。
しかし、確定申告は、あくまで自営業者と国との間の問題であり、被害者が加害者を裁判で訴えることとは無関係である。仮に実際に自営業者に過少申告の事実があったとしても、交通事故以前に、過少申告をしたことで被害者は加害者に何らの迷惑も及ぼしていないのである。したがって、加害者から、信義則違反を言われる根拠はない。結局のところ、損保会社の非難は、的外れの意見と考えるほかない。
逸失利益とは、交通事故の被害者が怪我の治療を終わって、これ以上良くも悪くもならない状態(これを「症状が固定した」と呼ぶことが多い。)に至った時点で、その被害者の体に残った後遺障害によって生じる損害のことを言う。
例えば、交通事故によって右膝に大怪我をした被害者に、右膝関節の機能に著しい障害が残って、自賠責保険で後遺障害等級10級11号の認定が出たとする。その場合、被害者の右膝には相当に重い障害が残存していることは間違いない事実であるから、仮に交通事故に遭わなかった場合と比べた場合、当該障害のために、その人が本来有していた労働能力が低下(喪失)したと考えるのが筋である。すると、労働能力喪失分だけ、その人が将来得るべき所得も低下する蓋然性も高くなったと理解できる。そこで、将来減少すると見込まれる所得を、現時点で補償するというのが逸失利益の性格である。
ところが、損保会社(及びその雇われ弁護士)は、上記のような明快な理論を理解しようとしないことが多い。その典型例は、たとえ事故被害者に後遺障害が残っても、所得が減少する事実が発生していない場合である。損保会社は、当人の所得が事故前と比べて減っていない以上、逸失利益の発生を認めようとしないのである。特に、被害者が公務員とか大企業のサラリーマンの場合がこれに当てはまる。
しかし、このような損保会社の考え方は完全な間違いである。
実は、この点は古くから差額説と労働能力喪失説との対立として有名な論点となっている。差額説は損保会社の考え方に親和性をもつ。交通事故がなかったならば得られたであろう収入と交通事故後に現実に得られた収入との現実の差額を損害と考える。
他方、労働能力喪失説とは、人の労働能力を一つの財産と考え、後遺障害による労働能力の喪失自体を損害と考える。これは、私の考え方に近い。
差額説が間違っている主な理由は、次のとおりである。
(1) 差額が生じるか否かは、症状固定の時点又はこれに近い時点では分からない。逸失利益は、将来の収入減少を補償するという性格のものであるから、はたして収入に悪影響があるか否かは、長期的に検証してみないと何とも言えないはずである。したがって、「現時点で収入が減少していないから」という理屈は、余り説得力がない。
(2) 公務員や大企業のサラリーマンのように、現時点で収入が減少していなくても、それは本人が人並み以上の努力をして体のハンディを補った結果である場合も多い。また、職場で特に配慮してもらった結果、減収が当面表面化していないだけのことである場合も少なからずあろう。このような場合に、目の前に減収がないからと言って、将来発生するかもしれない不利益を被害者に一方的に負担させる考え方はおかしい。
(3) 公務員のように法律で俸給表が決定されている被害者であっても、後遺障害を有している場合と有していない場合とでは、将来予測は全く同じではない。後遺障害のために従事できる職種が制限されたり、職務遂行能力が他人よりも低く評価されたりして、結果的にマイナスの人事評価を受ける可能性は相当あると考えられる。その場合、収入が将来減少する蓋然性が高い。
また、公務員の場合、身分保障制度が手厚いために収入減少が認められないことがある。その状態について、それは公務員制度が当人の損害を事実上カバーしている状態と考えることも可能である。このような場合に、損益相殺(被害者が損害賠償の原因と同一の原因によって利益を受けた場合に、被害者から当該利益を控除すること。例えば、被害者が、自賠責保険から損害賠償額の給付を受けた場合、それは既払金として賠償額から控除する。)とならないことは当然である。よって、制度上の保障によって、損害が事実上補てんされた結果として減収が認められない事態は、損害賠償額の算定に当たって特に考慮する必要がない。
(4) 減収の程度が自賠責保険の認定する後遺障害の等級よりも重い場合とのバランスを考える必要もある。例えば、上記の例で挙げた障害等級10級11号の場合、自賠責保険では、労働能力喪失率は27パーセントとされている。
しかし、被害者の現実の減収状況が50パーセントを超えていたような場合はどう考えるべきであろうか。この場合、損保会社は、今度は、手の平を返したように、さっさと差額説を放棄して、「被害者はせいぜい27パーセントしか労働能力を喪失していない。」と主張するであろう(この場合に、実際の減収割合である50パーセント超の喪失率を素直に認める損保会社はほとんど見かけない。)。これでは、「ご都合主義」と言われても致し方あるまい。
以上のことから、逸失利益は、基本的に労働能力喪失説に従って理解するのが正しい。
このような正しい結論に到達することは、事件によっては必ずしも容易なことではないが、私としても、日々の訴訟において担当裁判官の理解を得るよう努めているところである。

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.