
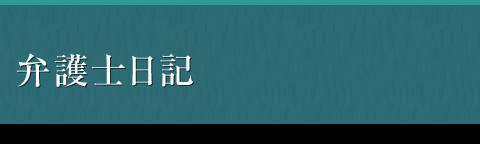
パソコンで弁護士事務所のホームページを見ると、実に多くの弁護士がホームページを立ち上げて、自分の事務所がいかに良い事務所であるかを宣伝している。弁護士の仕事の実情を知らない一般人が各弁護士事務所のホームページを見た場合、そこに書かれていることがどこまで真実であるのか、多少なりとも誇大広告気味となっているのかを正確に判定することは極めて困難である。
私が弁護士になった平成時代の初期においては、「いやしくも弁護士たる者、宣伝広告など出すものではない。そのようなことをすることはさもしい」と考えるのが当たり前であった。ところが、時代が変遷し、今では、宣伝広告を出すことはむしろ当たり前の時代となった。
このように、時間が経過すると、常識も180度変わるのである。
さて、これまで何回も取り上げてきたことであるが、交通事故を専門分野の一つとする弁護士事務所には、大きく二つのものがある。一つは、加害者側であれ、被害者側であれ、依頼があれば何でも引き受けるという事務所である。つまり、損保会社から事件の依頼があれば、加害者の利益を実現するため、つまり被害者に不利な結果が出るように頑張るという事務所である。
ただ、その事務所がそのような方針を取ること自体は、当該事務所の自由であって、他人からとやかく言われる筋合いのものではない。弁護士の自由ということである。
ただし、私は、そのようなやり方はしない。当事務所の場合は、あくまで被害者からの依頼に基づいて、依頼者の利益だけを最大限実現するという方針を昔から堅持している。損保と闘う、という理念を頑なに維持している。
したがって、損保会社からの依頼は全部お断りするようにしている(もっとも、最近ではそのような打診自体がないが・・・)。損保会社と直接の関連性はないが、私は、金力や権力にあぐらをかいて、好き勝手なことをやって他人に迷惑を及ぼしておきながら全く責任をとろうとしない団体や人物を極端に嫌う傾向があるのである。
なぜ、そのような姿勢をとるのか?と言われれば、私が合格した当時は、日本一の難関試験であった司法試験に合格し、せっかく弁護士になったのであるから、自分の理念(被害に苦しんでいる人々を救済するという理念)に合わない仕事に、自分のエネルギーを投入したくはない、ということに尽きる。
ここで、最初の話題に戻る。一般人が弁護士を選択する場合に、どのような基準をもって選択すれば、後で「しまった」ということにならないか?間違った委任をしないためには、3つのポイントがあると思う。
第1のポイントは、専門性である。交通事故訴訟に限らず、専門性を有しない弁護士に事件を依頼してはダメである。これを医師に例えた場合、胃の具合が悪いので診察を希望した場合に、患者は、果たして耳鼻咽喉科や眼科に行くだろうか?普通は行かない。行くとしたら、内科とか胃腸科であろう。また、専門性は、その弁護士が勉強熱心か否かということと大いに関係がある。勉強熱心な弁護士であれば、実務経験とともに専門知識が蓄積してゆくし、怠惰な弁護士の場合は、昔習った時代遅れの知識で事件を適当に処理してお終い、ということになる確率が高いと言える。
第2のポイントは、その弁護士がどれくらい熱心に依頼した事件に取り組んでくれるのか、という点である。いくら高名な弁護士であっても、自分は趣味のゴルフに没頭し、依頼者から引き受けた事件は、事務所で雇っている若い弁護士に丸投げということでは、とうてい依頼者の期待に応えることはできないであろう。
第3のポイントは、依頼者からの質問や疑問に丁寧に答えてくれるか?である。弁護士の中には、仕事が忙しいなどを理由に、依頼者が電話で質問をしても、迅速に回答しない弁護士がいるとのことである。このような不誠実な弁護士に事件を依頼することは、考えものである。仮にそのような情報が事前に分かるのであれば、依頼を止めた方が無難であろう。
弁護士日記の読者の皆さんは、依頼者の代理人となった弁護士が、裁判所と相手方の弁護士に提出する準備書面というものをご存じであろうか?
準備書面とは、訴訟で問題となっている事実関係とか、法律上の争点について、一方当事者の主張を書いたものであり、裁判を進める上で極めて重要な意味を持つ。
それは、交通事故を原因とする損害賠償請求訴訟を例にとれば、被害者が、どのような怪我をして、どのような損害を受けたかなどの争点について事細かく記載してあるからである。
原告のAが代理人を通じて準備書面を出した場合、その直後の法廷では、その準備書面を基に、次回の裁判の予定が立てられる。したがって、相手方である被告Bの代理人弁護士としては、裁判が行われる期日の前に、原告Aが主張している内容をよく読んで、あらかじめ裁判の当日にどのように被告Bの反論ないし主張を展開するかについて検討を加える必要がある。
そのため、名古屋地裁の交通部(民事3部)は、ことあるたびに、双方当事者は、おおむね1週間前までに準備書面を裁判所と相手方の当事者に送付するよう心掛けることを求めている。
そのような運用になっていることは、普通の弁護士であれば誰でも知っている常識である。したがって、特に、裁判所から注意を受けなくとも、一部の弁護士は、おおむね1週間前までに準備書面を提出しているようである。ところが、どの世界にも約束事を守ろうとしない輩がいる。私も、今までに、そのような心得違いをしている少なからぬ弁護士を相手にしてきた。
私の場合は、直接、当人に対し電話で注文を付けるか、あるいは、法廷内で裁判官に対し、「準備書面を次回期日の1週間前までに提出するように相手方弁護士に対し、訴訟指揮をされたい。」とお願いすることが多い。
大半の代理人弁護士は、私がこのような意見を述べると、特に異論なく了解されるので、その後は、問題なくおおむね1週間前までに準備書面を提出してもらっている。
ところが、ごく稀に、「他にも多くの事件を抱えていて忙しい」、「依頼者に書面を確認してもらっているため時間がかかる」、「他の弁護士の中には期日の当日に準備書面を出す人もいるではないか」などの、全く理由にもならない屁理屈を捏ねる事務所が現にある。
このような事務所は、「提出が遅れております。今後気を付けます」という当たり前の言葉が最初に出て来ない。まず、自分の正当性を印象付けようとして、上記のような無用の弁解を行うのである。準備書面とは、単に、自分の側の主張を相手方及び裁判所に伝えるだけのものではなく、相手方の当事者及び裁判所が、円滑に訴訟を進行させるためにも必要である。
つまり、相手方としては、裁判の期日よりも前に内容を点検して法廷に臨む必要があるのである(おそらく、裁判所も同様であろう。)。
仮にそのような根本が少しでも分かっておれば、上記のようなおかしな言い訳は出てこないはずである。逆に言えば、根本が全く分かっていないから、最初に言い訳から始まるという見苦しい態度に出るわけである。私としては、このような事務所を相手にしたときは、通常の場合以上に、依頼者の利益を図るべく、訴訟に力を入れることにしている。
前回取り上げた事案は、転用事業者Bが、D県知事の農地法5条許可を受けて、所有者Aから農地を購入したが、Bはその直後、経営不振に陥って許可申請にかかる転用事業を行うことができなくなった。近所に住むCから、当該農地を買い受けて転用したいという希望が出ている。この場合、Bとしてはどうすればよいか?という事例であった。
今回取り上げるのは、Bは、D県知事から5条転用許可を受けたが、諸般の事情のため転用事業を自ら行うことができなくなった。ところが、誰も転用事業を引き継いでくれないという場合である。
この場合、D県知事としては、5条転用許可処分を受けたBに対し、すみやかに申請にかかる転用事業を行うか、あるいは事業を引き継いでくれる第三者との間で転用事業計画変更申請を出すように行政指導を行うことが通常である。
問題は、転用事業を引き継いでくれる第三者が不在の場合である。その場合、Bは、転用事業を行う法的な義務を負うか?答は、法的な義務は負わないということである。なぜなら、Bが受けた転用許可処分は、Bが転用事業を適法に行うことができるための要件にすぎないからである(さらに、5条許可の場合は、権利設定又は権利移動を有効とする効果もある。)。転用許可処分を受けたからといって、Bとしては、何が何でも転用事業を行う義務を負わされるものと考えることはできないのである。
仮に、D県知事がいったん出した5条許可を取り消しても、その処分は、取消処分ではなく撤回処分の性格を持つため、前回解説したとおり、遡及効はない。撤回時点から将来に向かって処分の効力が失われるだけである。
したがって、例えば、Bが前者Aから譲り受けた所有権は、依然としてBにとどまる。Bは転用許可にかかる農地の権利を有効に保持することができる。ただしこの場合、Bとしては、以後、事情が変わって転用事業を行うことができる状況になったとしても、もはや取消済みの過去の5条転用許可処分に基づく農地転用を行うことはできない。
仮に、新たに転用事業を行いたいときは、新たに4条転用申請を行うべきである。ただし、この場合、過去に5条許可の取消前歴のあるBについて、D県知事としては、農地を転用事業の用途に供する確実性がないなどの理由で、容易に4条許可を出そうとしない態度を示す可能性が高いであろう。
今回からしばらくの間、私の専門分野である農地法に関する質問を取りあげて、専門家の見地から答を出してみたいと思う。
今回の事案は、転用事業者Bが、D県知事の農地法5条許可を受けて、所有者Aから農地を購入したが、Bはその直後、経営不振に陥って許可申請にかかる転用事業を行うことができなくなった。近所に住むCから、当該農地を買い受けて転用したいという希望が出ている。この場合、Bとしてはどうすればよいか?という事例である。
農地の譲受人であるBは、転用事業を行うという目的・理由で農地をAから購入したのであるから、Bとしては、転用許可申請書に記載したとおりの転用事業を行う必要がある。つまり、D県知事は、Bが5条転用事業を行うことを条件として許可処分を出しているのである。したがって、仮に、Bが転用事業を行わないときは、D県知事としては、これをそのまま黙認することはできない。
農地法51条1項は、その2号で、農地法5条1項の許可に付した条件に違反している者に対し、許可を取り消すことができるとしている。仮に、D県知事が、許可を取り消した場合、A・B間の法律関係に重大な影響が及ぶことがあり得る。そこで、「許可の取消処分」の意味が問題となる。
許可の取消処分が、文字通り「取消し」という法的性質を持つと見た場合、許可処分は処分時に遡及して効力を失うということになる。しかも、この許可が法律行為の効果を補充して有効たらしめる効力を持つことを考え併せると、A・B間の農地譲渡行為も遡及して無効とならざるを得ない。
他方、この取消処分を「撤回」処分とみた場合、撤回処分の効力は将来に向かって生ずるということになって、遡及はしない。つまり、A・B間の農地譲渡行為は依然として有効ということになる。上記の場合は、処分時に瑕疵があった、つまり許可を出すことがそもそもできなかったという場合ではないから、撤回処分と考えるべきである。
Bとしては、D県知事による5条許可の取消しという最悪の事態を避けるためにはどうすべきか?本件の場合、近所に住むCから、問題となっている農地を買い受けて転用したいという希望が出ているのであるから、BとCは、連署の上で事業計画変更申請を行い、D県知事に承認してもらう方法がある。また、同土地は、依然として農地性を持っているから、事業計画変更申請と同時に、B・Cは、連署の上で5条許可申請書をD県知事に提出し、5条許可を受ける必要がある。
仮に、今回のCのような存在が全くなかった場合、Bは、5条許可を受けたままの状態を継続するほかない。そして、仮に、Bが、D県知事からの、「早く転用事業を行うべきである」という内容の行政指導にも全く応えようとしない場合、D県知事としては、5条許可を取り消すほかないことになろう。
しかし、上記のとおり、仮にD県知事が5条許可を取り消したところで、農地の所有権は既にBに移転してしまっている以上、依然としてBにあると考えられる。
なお、AからBに対する移転登記については、Bが転用許可を受けた後に、5条許可書を添えて法務局に対し移転登記を申請していれば、移転登記は可能と考えられる。
D県知事による5条許可取消処分の前に、既に、Bが所有権移転登記を済ませていれば、登記名義もBのままということにならざるを得ない。Bにとっては、農地所有権を確保し、かつ、登記名義(対抗要件)も備えた事実状態が継続するということになる。
今回は、人身傷害保障保険を取り上げる。今回紹介する判例は、大阪地裁平成25年1月24日判決である(交民46巻1号103頁参照)。
人身傷害補償保険については、既に、最高裁の平成24年2月20日判決が、裁判基準損害説を採用することを明言したことから、決着が付いている。この最高裁判決は、保険会社の保険代位の範囲について判断を示したものであるが、被害者の立場からすると、人身補償保険会社が、どの範囲で損害賠償請求権を代位取得できるかの問題は重要でなく、被害者側としては、人身傷害補償保険(以下「人傷保険」という。)と、損害賠償金の受領の先後(順番)によって、受け取れる金額に変動が生ずるか否かに絞られる。
この点については、法曹会発行の「最高裁判所判例解説平成24年度(上)」で調査官が解説しているとおり、原則的に、人傷保険を先に受け取った方が、被害者が受け取れる賠償金額が多くなるという結果が出ている。
今回の大阪地裁の判決であるが、金額の端数を切って数字を簡略化して説明すると、次のようになる。判決が認めた被害者の過失割合は30%である。判決が認定した損害額の合計(ただし、弁護士費用を含まず。)は、過失相殺を行わない場合、2794万円である。これが、裁判基準損害額となる。
また、損益相殺として、被害者に対し、自賠責保険から461万円の支払があった。さらに、被害者に対し、人傷保険から1926万円の支払があった。ここで、判決は、こむつかしい議論を経た上で、被害者の損害額は、407万円であるとした。
しかし、この点を単純に考えると、裁判基準損害額が2794万円なのであるから、被害者としては、ともかく総額2794万円を受領すれば満足することになる。したがって、2749万円から、自賠責保険の461万円と、人傷保険の1926万円を控除した残額さえ、判決で認められれば足りるという話に落ち着く。すると、2794万円-461万円-1926万円=407万円となる。
大阪地裁は、これに弁護士費用1割相当額を加算して、被害者である原告の損害額は、最終的には446万円であるとした。なお、本事故における被害者の過失割合は30%であったが、仮に、数値に変動が生じても(例えば、過失割合が10%であっても20%であっても)、上記金額(407万円)に変動はないと考えられる。
また、判決は、保険会社の代位取得額についても、人傷保険1926万円と過失相殺後の損害賠償金額1956万円の合計額である3882万円が、裁判基準損害額2794万円を上回る場合に限って、上回る額に相当する額の範囲内で代位取得するとして、1088万円となるとした。
以上のように、被害者が、先に人傷保険を受け取っておれば、被害者としては、人傷保険1926万円、自賠責保険461万円、判決額446万円の合計2833万円を手にすることができるわけである。ただし、被害者に過失が全くない場合は、人傷保険を先に受け取ると、かえって不利な結果となる。
なぜなら、上記の場合、裁判基準額2794万円から自賠責保険461万円を控除した正味2333万円について、弁護士費用233万円(ただし、名古屋地裁の場合はより少額となる。)を加算すると、計2566万円となり、これに既に受け取っている自賠責保険461万円を足すと、合計で3027万円となるからである。つまり、先に人傷保険を受け取った場合と比較して、より高額となるからである。

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.