
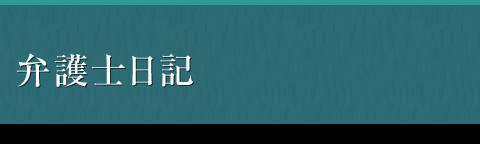
今年になって世界が一番懸念していたウクライナ問題について、遂に、ならず者国家であるロシアは隣国ウクライナへの軍事侵攻を開始した(2022年2月24日)。
このような事態が起きるかもしれないと予想することは、日頃から世界情勢に関心を払っておれば、そんなに難しいことではない。現に私は本年1月の時点で予想していた。侵略を開始した理由は、これまでも述べたことであるが、ロシアとしては、絶対にウクライナがNATOに加盟してもらっては困ると考えているからである。
しかし、主権国家であるウクライナが、どのような途を選択するかは、ウクライナ国民のみが決定できることであり、他国がこれに口を出すことはできない。純粋に国内問題だということである。しかし、強盗ロシアは、そのような国際法の原則を破ってウクライナへの侵略を開始した。
ロシアは、軍事侵攻を正当化するため、ウクライナの一部である「ルガンスク人民共和国」と「ドネツク人民共和国」について国家承認を行い、その国からの軍隊の派遣要請に基づきロシア軍を派遣したという理屈を並べている。しかし、そのような間違った理屈を本当に信じる者など、独裁者プーチン以外にはいないと思われる。
なぜなら、適法な国家承認を行うには、対象国が国家の資格を具備していることが国際法で求められているからである。手元にある「プラクティス国際法講義第3版」(柳原正治ほか編)83頁によれば、国家の資格要件として、1933年のモンテビオ条約1条が、➀明確な領域、➁永久的住民、➂政府、➃外交能力(独立)を掲げているからである。
しかし、上記の地域は、いずれも満たしておらず、今回のロシアの国家承認は、いわゆる「尚早の承認」に当たり国際法上違法である。分かりやすい例をあげると、ロシアと同じ独裁国である中国が、「沖縄国」を国家承認し、その「沖縄政府」の要請に基づいて中国人民解放軍を沖縄に派遣するようなものである。このような馬鹿げた理屈は、まともな日本人としては認める余地がない。
本来であれば、国連が事態の解決に乗り出すべきであるが、ロシアは国連の常任理事国であるため、国連がロシアに対し正式に軍事的な制裁をかけることはできない。ロシアが拒否権を発動するからである。このように、常任理事国が絡む紛争に関する限り、国連は全く役に立たない組織となっている。
このような緊迫した国際情勢のさなか、国会(参議院予算委員会)では、左翼政党の議員による実のない質問が次々と発せられた。質疑ということで、岸田首相や各省の大臣に対し、さも得意げに質問をしている「勘違い」議員の姿を見て、本質はお山の大将プーチンと同じだと実感した。こんな輩は、早く国会から去って欲しいものである。
無意味な国会質疑に時間を浪費することは、国家にとって損失である。政府の閣僚を国会に呼ぶことは基本的にあっても良いが、拘束時間が、諸外国と比べて長すぎる。本当に、日本の国会ほど、その存在理由が希薄な機関はないのではなかろうか。国の諸政策は、すべて霞が関の各省庁の官僚が作成してくれるのである。官僚が国家運営に必要な事項は全部お膳立てをしてくれるのであるから、別に国会議員などいなくても、国家の維持・発展には全く支障がないということである。
もちろん、政策に誤りがあり、国民が迷惑を被っているような場合は、国会として政府に対し是正を申し立てる必要はある。しかし、是正を述べるだけであれば、国会議員など、衆参合わせて200名程度で十分であろう。現在は、無駄飯を食うことができる議員が多すぎる(いても、いなくても国益に全く影響しない議員が大半である)。法律で余りにも過剰な議員定数が定められているため、おかしな人間でも、間違って当選できてしまうということである。
話が逸れたので、戻す。今回、独裁者プーチンは、悪知恵を働かせていろいろと謀略やシナリオを練った上で、今回の作戦はうまく行くと自信をもっているようである。しかし、国際法を踏みにじり、国際秩序を破壊し、戦争を堂々と起こそうとする今回の作戦は、あたかもナチスドイツのヒットラーがやったことと本質は同じである。ヒットラーがどのような悲惨な最後を迎えたかは、改めて説明するまでもなかろう。嘘つきプーチンには最大限の厳しい懲罰を与える必要がある。
独裁者というものは、ほぼ例外なく、自分の考えていることだけが正しく、自分を批判する者は全部間違っている(だから粛清する必要がある)と過信するものである。また、嘘の情報をあたかも本当の話のように発信するものである。したがって、プーチンの言うことは絶対に信用してはならない。全部が嘘で固められている。さらに、プーチンは核兵器の先制使用をも明言している。世界の国を脅迫しようとするとんでもない発言である。独裁者プーチンは頭がおかしくなったとしか言いようがない。
今やロシアは、世界(除く中国)の敵となった。ロシアは緒戦には勝ったように見えるが、最終的には破滅に向かうであろう(2月24日は「ロシア破滅の日」)。ロシアを破滅させるためには、西側民主主義国家は、今後、ウクライナのレジスタンス活動を強力に支援する必要がある。私は、悪魔のようなプーチンを絶対に許すことはない。独裁者プーチンは、いずれ暗殺されるか、自殺するかの運命をたどると予想する。
(追記)2月25日になって、いよいよロシアは、ウクライナへ国土への全面的侵略を開始した。最初からプーチンの狙いは、ウクライナの現政権を倒し、親ロシアの傀儡政権を樹立し、ロシアの意のままになる国にしようとしていたことが明白となった。これはウクライナの国家主権を完全に侵害するものであり、絶対許されないことである。何としても異常人格者であるプーチンを破滅させる必要がある。
1 Aが所有する農地甲があり、その農地の賃借人Bが遺言を作成しようと考えた場合、大きく分けて「相続させる」遺言と「遺贈する」遺言の二つが考えられる。そこで、これらの遺言について何か違いがあるのか否か検討する。
まず、相続させる遺言であるが、遺言で受益する者は相続人に限定される。非相続人が指定されることは想定できない。そして、相続させる遺言には二通りのものがあり、受益相続人が相続する財産が特定されている場合と、特定されていない場合である。
前者は、民法上は特定財産承継遺言と呼ばれる(民1014条2項)。例えば、Bの所有する土地・建物を相続人の一人であるCに相続させる場合がこれに当たる。相続が開始つまりBが死亡すると同時に、当然に土地・建物の所有権はCに移転する。相続人間で遺産分割の手続を踏む必要はない(民906条)。登記手続は、Cの単独申請で足りると解される。
一方、後者は、相続される財産が特定されていない。ではどのような場合に生じるかと言えば、Bが相続分の指定をした場合である。例えば、Bの相続人として、長男C及び次男Dの二人が存在していたところ、「Cに3分の2を、Dに3分の1を相続させる」と遺言した場合がこれに当たる。この場合、具体的にどの遺産が誰に相続されるのかは遺言だけでは明確ではない。そのため、後日、遺産分割協議を行って遺産の帰属を確定させる必要がある。
2 このようにBによって相続分の指定が行われ、Bが死亡したものの未だ遺産分割の手続が完了していない場合、生前Bが有していた賃借権(耕作権)は誰に帰属することになるか。農地甲について存在する賃借権もまた一種の財産権である。そして、賃借権は債権であり、共同所有の状態に置かれていると解されるが、このような状態は準共有と呼ばれる(物の共有ではなく、権利の共有であるため準共有となる。)。つまり、C及びDは、被相続人Bが生前に保有していた賃借権を共同で承継した状態にあるということである。
この場合、C又はDは、どの範囲で農地甲を耕作することができるのかという問題がある。この点に関しては、最高裁判例は、遺産共有も通常の物権法上の共有と性質を異にするものではないとの立場をとっていることから(最判昭30・5・31)、通常の共有と同様に解すれば足りる。すなわち、民法249条によって、各共有者は、共有物の全部についてその持分に応じた使用をすることが認められる。
上記の事例の場合、C又はDは、平等に農地甲の全部について耕作する権利がある。ただし、持分による制限はあると解されるので、仮にCが農地甲の全部を耕作した場合、特にDがそれを了解していたような場合を除き、Dから、Cに対し同人の持分を超えた部分の使用について使用料の支払い要求があったときは、これに応じる義務があると解される(最判平12・4・7)。
では、C又はDは、自分たちが共有する賃借権を、他人Eに譲渡することができるであろうか。結論を先に言えば、賃貸人Aの同意がない限り、賃借権を勝手に譲渡することはできない。そのことは、民法612条1項の規定から明らかである。
3 次に、農地甲の賃貸人Aは、誰に対し賃貸料(小作料)を請求することができるか、という問題がある。これはC及びDの側から見た場合、賃借料をどのような割合で負担するかという問題である。最高裁判例は、賃料債務のような可分債務は、法定相続人の相続分に従って承継されるとしているため(最判昭34・6・19)、C及びDに対し半額ずつ請求することができると解される。
なお、CとDが遺産分割を行って、例えば、土地と建物の所有権はCが取得し、他方、農地甲の賃借権はDが取得するというように話がまとまった場合、以後、賃借料全額の支払いはD一人が行うことになる。
4 次に、遺贈である。遺贈によって財産をもらうことができる者を受遺者という。遺贈の場合、相続人の場合はもちろんのこと、非相続人であっても受遺者となり得る。また、法人であってもかまわないとされる。遺贈には、遺贈の目的物が特定されている特定遺贈のほかに、目的物が特定されない包括遺贈というものがある(民964条)。包括遺贈は、さらに全部包括遺贈と割合的包括遺贈に分類される。そして、包括遺贈を受けた者を包括受遺者という。
割合的包括遺贈とは、相続財産の分数的割合による遺贈であり、例えば、Bが「他人Fに対し相続財産の3分の2を遺贈する」と遺言したような場合である(他方、「Fに対し相続財産の全部を遺贈する」と遺言したような場合は、全部包括遺贈となる。)。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(民990条)。あたかも相続人と同じような立場に置かれ、相続の承認・放棄の規定が適用される(民915条)。仮に上記の事例で、Fが遺贈を拒否したいと考える場合は、それを放棄することも可能である。
なお、Bが例えば、「Fに対し相続財産の3分の2を遺贈する」と遺言した場合、Fは本来の相続人C及びDと共に、遺産分割の当事者として分割協議に参加することが認められる。遺産分割の結果、仮にFが土地と建物の所有権を取得することになった場合、移転登記手続は、登記権利者Fと登記義務者である相続人C・Dとの共同申請となる。
最近、書店で升田純著「名誉毀損 判例・実務全書」(民事法研究会、税込み6160円、全537頁)を購入し、本日さっそく読んだ。目的は、この本の題名に関連する紛争が最近生じたためである。そこで、改めて名誉毀損に関する法律の原理・原則を確認しようとしたわけである。まだ、基礎理論を論じた総論部分の100頁しか読んでないが(各論は判例の紹介)、非常に役に立った。私は、中央大学法科大学院の升田教授とはもちろん面識はないが、升田氏は、これまで主に実務者向けの優れた法律書を数多く出しておられる。日本有数の実力派学者といっても過言でない。
そこで、勝手ながら本の内容を少し紹介させていただく。まず、名誉の定義であるが、「人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値であり、社会から受ける客観的な評価である」と一般に解されている(16頁)。一方、人が自分自身に対して有する主観的な名誉感情も、民法の不法行為上保護されている。また、その侵害は、場合によっては刑法231条の侮辱罪にも当たることがある(30頁)。
人の名誉が毀損された場合、被害者が加害者に対し損害賠償等の請求をしようとした場合、民法では709条、710条および723条が根拠条文となる。そして、名誉毀損という不法行為が成立するためには、➀加害者に故意または過失があること、➁名誉権(名誉)の侵害があること、➂損害が発生したこと、➃故意・過失と損害発生の間に相当因果関係があること、の4つの要件を満たす必要がある(29頁)。
名誉毀損(名誉権侵害・名誉侵害)の具体的手段については、口頭による発言、文書に記載する方法、インターネット上に掲示するなどの方法がある(33頁)。
ここで、名誉権の侵害について、公然と行われる必要があるか否かという論点がある。刑法上の名誉毀損罪は構成要件上、公然と行われる必要があるが、民法上はそのような条件は特に置かれていないため、公然性は要件とならないと解される(同頁)。
名誉毀損の免責要件については、有名な最高裁判例がある(最判昭41・6・23)。それによれば、問題とされた表現が、公共の利害に関する事実にかかり、もっぱら公益を図る目的に出た場合には、適示された事実が真実であることが証明されたときは、違法性がなく、不法行為は成立しない。仮に真実であることが証明されなくても、行為者において「その事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である」とされている(41頁)。
このように、表現が公共目的をもったものである場合は、たとえ真実であること自体の証明ができなくとも、真実であると信じたことに相当の理由があれば免責されることになる(72頁)。相当性の要件の有無によって裁判の勝敗が決まることもあるということである。例えば、しばしば問題になる新聞、週刊誌、テレビ等のマスメディアによる名誉侵害については、「情報として適示した事実に関する取材の範囲・方法・内容が問題になることが多い」とされる(同頁)。
この場合、被告とされたマスメディアが、自分の相当性を立証するためには、取材源、取材の範囲・経緯、取材の方法・内容等の事情を具体的に明らかにすることが重要である(73頁)。
例えば、新聞記者Aが、ある人物Bから、他人Cがオレオレ詐欺の主犯格であるとの話を聞き、それをそのまま鵜呑みにして、実は何ら犯罪に関与していないC氏について、「C氏はオレオレ詐欺グループのリーダーである可能性が濃厚」という記事を出した場合、C氏に対する名誉毀損行為が成立する(なお、虚偽の話をしたBも共同不法行為責任を問われる可能性がある。また、Bのような人間に限って、自分の身に危険が及ぶと、そのようなことをAに話した覚えは一切ないと否定し、逃げてしまうのが普通である。)。
この場合、記者Aとしては記事を書く前に、最低限、対象者であるCにも取材を申し込み、Cの言い分も確認する必要があったことはもちろん、Bと利害関係を持たない第三者Dにも取材をかけ、本当にBが言っているような事実があったかどうかを慎重に吟味する必要があった。つまり、裏付けをとる必要があったということである。十分な証拠をそろえた上で、「ほぼ間違いない」と確信して発表した場合に限って相当性(免責事由)が認められる場合があるということである。
升田氏は、被害者が加害者の責任を追及しようと訴訟を提起した場合、非常に重要なポイントを指摘されている。それは、名誉毀損を行う者は、一部の例外を除き、「特定の動機・目的の下、特定の方向で被害者を誹謗中傷しようとするものであり、文書の記載も、放送も、発言も、これらの意思に従って行われているものであるから、・・・記載等の全体が名誉毀損等の意思に従って構成されることを重視した主張・立証を展開することが重要である」との箇所である(101頁)。要するに、加害者の全体的意図を裁判官に十分に理解してもらうことが大事だということである。
升田氏も言っておられるが、名誉毀損のトラブルは、「誰でも、いつでも、どこでも被害者になり得るし、加害者にもなり得る」(5頁)。特に法律を専門とする弁護士の場合、自戒の念を込め、日頃から無用のトラブルに巻き込まれないよう脇を固めておく必要があろう。
本日(2022年2月17日)のFNNニュースによれば、今月15日に、林芳正外務大臣は、ロシアの閣僚とテレビで経済協力についての会合を行ったという事実があるようである。この林外相の動きに対し、自民党の高市早苗政務調査会長は批判を加え、G7(先進7カ国)の結束を乱すものであって、強い懸念を覚えると述べたという。
このニュースは事実である可能性が極めて高い。そうすると、一体、林外相は、何を考えてこの時期にロシアと経済協力に関する協議をしたのであろうか?理由が全く分からない。なぜなら、現時点で、ウクライナをめぐってロシアが軍事行動をとる危険が非常に高くなっているからである。1か月前のブログでも指摘しておいたとおり、ロシアは、ウクライナのNATO加盟を絶対に容認しないという主張を繰り返し行い、ウクライナのNATO加盟を阻止するために、ウクライナへの軍事侵攻を現に企てているのである。つまり、現政権を倒し、親ロシアの人物を傀儡として大統領に据え、自分たちの勝手な要求を実現しようとしているのである。
このような勝手な要求は、絶対に認めるわけにはいかない。ウクライナは主権国家であり、NATOに加盟するか否かはウクライナの国民が決めることだからである。ロシアの行動は、まさにこれから強盗を働こうとしているギャング(暴力団)のようなものである。
ここで、ギャング・ロシアの勝手な行動を阻止するためには、ウクライナが軍事力を増強して自国を守るということが第1である。しかし、軍事力というものは、一朝一夕に整備できるものではなく、時間をかけて徐々に整備する以外にない。緊急事態が発生したからといって、急に整備できるものではないことは、普通の中学生でも分かることであろう。仮にウクライナに日本国憲法9条2項(戦力の不保持)のような憲法があったとしても、戦争を抑止するという観点からは、そのような憲法の条文は紙くず以下の価値もない。むしろ有害である。
そこで、外交の出番となる。外交とは、話合いによる問題(懸案事項)の解決ということである。周知のことであるが、外交で重要なことは、世界の多くの国を味方につけるということであり、とりわけ先進国の結束が重要となる。つまり、米、英、仏、独、伊、日、カナダの先進7カ国の調和・協力が必要となる。7カ国とEUが一致してロシアに圧力をかけることによってロシアの軍事侵攻を阻止しようということである。具体的には経済的な制裁をかけることでロシアの横暴を止めるということである。
そのような状況下で、日本がロシアと経済協力の会合を開いたということは、先進国の結束を乱すものであることは明白である。結果、ロシアによるウクライナ侵攻の危険性が高まるという「悪い事態」をもたらすのである。
なぜ、この時期に会合を開いたのかを問われた外務省は、「前から予定されていた会談だったから」と釈明したと聞く。この話を聞いて、本当に日本の外務省ほどダメな役所はないと改めて思った。既に決まっていることだから、今更変更できないという理屈は、役人根性の悪い面を如実に示している。
外務省には、「臨機応変」という言葉はないようである。霞が関の多くの省庁の中でも、ダメぶりにかけては断トツといえよう(ただし、これは私の主観的評価であり、客観的なものと主張しているのではないことに注意)。そのくせ、気位の高さだけは他を寄せ付けない。大使は、「閣下」と呼ばれるのが普通の取扱いと聞く。大使経験者は、退官後であっても、礼儀上、「大使」と呼ばれるのが当たり前となっているようである。このような古びた不合理な仕来りが今でも堂々と通用しているのが外務省である。
ここでいう「ダメ」とは、日本の国益を真剣に考えていないという意味であり、また、一般の日本国民からみた場合、過去の前例・決定を盾にとって何も解決しようとしない怠慢さであり、さらには、多額の海外在住手当をもらっておきながら、外国にある日本大使館の中で一体どのような仕事をしているのか具体的な中身が不明という意味である(私も昔観光で訪問したことがあるリトアニアの地で、人道主義の立場から外務省本省の意向に逆らって、不眠不休でユダヤ人に対しビザを発行し続けた杉原千畝氏の爪の垢でも煎じて飲んだらどうであろうか。)。また、例えば、戦後の竹島問題についても、客観的事実として韓国が日本の正当な領土である竹島を侵略したことが明らかであるにもかかわらず、強力・有効な対抗策を全く講じてこなかった。このことからも、日本の外務省の無為・無策ぶりは明白である。「遺憾であり、強く抗議する」などという常套文句は、木偶の坊であっても言える。日韓議連というような日本の国益を軽視した政治家の団体が、外交政策に悪い影響を与えたとしても、外務省の無能ぶりは弁護のしようがない。
その外務省の長が林芳正氏である。林氏をみていると、学歴・経歴には確かに素晴らしいものがあるが、その発言内容は、「生ぬるいお茶」のような感じであり、尖ったものが全くない。つまり、迫力が全く感じられない。また、外見上は態度が落ち着いているといえば聞こえが良いが、別の見方をすれば、何か茫洋としたイメージがあり、腹の中では何を考えているのか容易に推測できないという不気味さがある。かねてより林氏は親中派であることでも知られている。こうなってくると、親中・親ロ派の人物ということになりそうである。岸田総理がなぜ林氏を外相に起用したのか、全く理由が分からない。岸田氏も人を見る目がないものである。
私が見たところ、林氏は何事も無難に足して2で割るというようなタイプではないかと考える。平時の霞が関の実務はこれでも済むかもしれない。しかし、今後、自分の身を捨てても日本を立て直そうという気概はないと感じた。将来、日本国の首相になる可能性はきわめて低いと予想する。
(追記)今回、林外相に対しマイナス評価を下したが、林外相よりも酷いのは、前外相・現自民党幹事長の茂木氏である。茂木氏は、外相時代に中国の外相王毅と会談したことがある。その際、王毅は尖閣諸島の領有問題について、日本の立場を否定するとんでもない発言をした。その際、茂木氏は、へらへらと笑って済ませた(少なくとも、その場で直ちに横暴な発言をした王毅に対し強く抗議したという事実は確認されていない。)。このような卑屈な態度は、国益を守る気概がもともと希薄であることから生じたものと推測される。茂木氏だけは、絶対に日本国の首相にしてはならない。
1 最初に設例を示す。農地甲の所有者であるAは、当該農地をDに賃貸していた。賃料(いわゆる小作料)は、毎年12月31日までに当該年分の賃料を支払う約束(後払いの約束)となっており、賃料の額は年間10万円であったとする。ある年、Dが当該年分の賃料を支払期限である年末までに支払わないまま年を越してしまったところ、年を越した1月1日にAが急死し、子B及びCが相続人となった。
この場合、農地甲の所有権及びその賃料請求権は、相続人であるB及びCに相続される。まず、農地甲は不動産であることは疑いない(民86条1項)。不動産である農地の所有権は、Aの死亡つまり同人について相続が発生すると同時に、当然にB及びCの二人の相続人に引き継がれる。この場合、農地法3条許可を受ける必要はない。相続は意思表示によって発生するものではなく、人の死亡という事実に基づいて当然に発生するものだからである(民896条)。
では、農地甲の所有関係はどうなるのであろうか。B及びCは、いずれもAの子であるから法定相続分は同じであり、Aが遺言を残して二人の相続分を変更したというような特別の事情がない限り、各人が2分の1の農地所有権を承継取得する。この場合は、遺産共有という状態に置かれる。遺産共有とは、遺産分割が終わるまでの暫定的な法的状況を指す。遺産分割の原則については民法906条に規定があるが、BとCの協議がまとまる限り、農地甲をどのように分けても適法である。例えば、Bが農地甲の所有権の全部を取得するという内容の分割をしても問題ない。この場合、Bの単独所有となる。
2 次に、賃料請求権はどうなるのか。その前に賃料請求権の性格を確認する必要がある。民法88条2項は、「物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする」と定める。法定果実とは、土地や建物などの不動産、あるいは自動車などの動産を他人に貸した場合に対価として受ける賃料などのものを指す。物から発生する収益であるということから、法定果実と呼ぶ(ただし、私見によれば、このようなものを、あえて「法定果実」として民法典に定めておく必要性は薄いのではないかと考えられる。)。
また、法定果実の帰属について民法89条2項は、「法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する」と定める。例えば、土地の所有権者兼賃貸人が、賃貸期間の途中で変更した場合は、期間中の賃料を期間の長短に応じて前所有者と現所有者で分配することになる。ただし、契約によって特約が定められている場合はそれが優先する。
3 ここで上記の質問に話を戻す。前記のとおり、賃貸人Aが死亡することによって相続が開始し、亡くなったAが賃借人Dに対して有していた1年分の賃料請求権も農地甲と同様、相続人B及びCに相続される。この賃料請求権は、金銭の支払いを目的とするので金銭債権に当たる。
問題は、この賃料請求権が共有債権(共有財産)になるのか否かである。最高裁判例はこれを否定している。すなわち、最高裁平成17年9月8日判決は、「遺産である賃貸不動産を使用収益した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である」と判示している。
このことから、上記設例でいえば、B及びCは、各自5万円の金銭債権を確定的に取得していると解される(一部に「共有財産」になると誤解している者もいるようであるが、常に正確な法解釈を心がけて欲しいものである。)。なお、上記判例の中で、分割債権という用語が出ているが、根拠は民法427条にある。数人の債権者がある場合に、債権は平等の割合で分割されるという定めである(ただし、最高裁昭和24年4月8日判決は、相続の場合は法定相続分の割合で分割されるとしている。)。
4 ここで、仮に賃借人Dが、相続人の一人であるBから、「自分に10万円全額を支払って欲しい」と要請され、軽率にも、Bに対して10万円を支払えば債務がすべて消滅すると勘違いし、10万円全額を支払ってしまった場合はどうか。この場合、B・C間で賃料の受領権限をBに一任するというような特約がない限り、Cに帰属している5万円については、原則として支払いが無効となると解される。つまり、あらためてCから支払いを求められた場合に、Dはこれに応じなければならない(二重払いのリスク)。したがって、Dとしては、無用の不利益を被らないようにするためにも、慎重な行動が求められる。
5 仮にAが死亡時から丸1年が経過した時点で遺産分割協議が成立し、Bが農地甲のすべての所有権を継承することで話がまとまった場合、賃料請求権はどうなるか。まず、上記最高裁判例によれば、Aが死亡した時点で発生していた賃料債権はもとより、死亡後、遺産分割協議中の期間1年分の賃料債権も、やはり分割単独債権としてB及びCにそれぞれ帰属すると考えられる。一方、遺産分割が成立した時点で農地甲はBの単独所有となるため、それ以降に生ずる賃料債権はB一人に帰属すると解される。

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.