
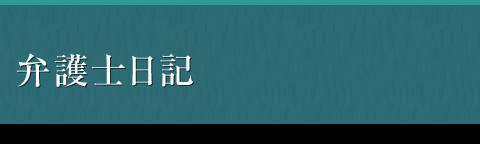
最近、書店で升田純著「名誉毀損 判例・実務全書」(民事法研究会、税込み6160円、全537頁)を購入し、本日さっそく読んだ。目的は、この本の題名に関連する紛争が最近生じたためである。そこで、改めて名誉毀損に関する法律の原理・原則を確認しようとしたわけである。まだ、基礎理論を論じた総論部分の100頁しか読んでないが(各論は判例の紹介)、非常に役に立った。私は、中央大学法科大学院の升田教授とはもちろん面識はないが、升田氏は、これまで主に実務者向けの優れた法律書を数多く出しておられる。日本有数の実力派学者といっても過言でない。
そこで、勝手ながら本の内容を少し紹介させていただく。まず、名誉の定義であるが、「人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値であり、社会から受ける客観的な評価である」と一般に解されている(16頁)。一方、人が自分自身に対して有する主観的な名誉感情も、民法の不法行為上保護されている。また、その侵害は、場合によっては刑法231条の侮辱罪にも当たることがある(30頁)。
人の名誉が毀損された場合、被害者が加害者に対し損害賠償等の請求をしようとした場合、民法では709条、710条および723条が根拠条文となる。そして、名誉毀損という不法行為が成立するためには、➀加害者に故意または過失があること、➁名誉権(名誉)の侵害があること、➂損害が発生したこと、➃故意・過失と損害発生の間に相当因果関係があること、の4つの要件を満たす必要がある(29頁)。
名誉毀損(名誉権侵害・名誉侵害)の具体的手段については、口頭による発言、文書に記載する方法、インターネット上に掲示するなどの方法がある(33頁)。
ここで、名誉権の侵害について、公然と行われる必要があるか否かという論点がある。刑法上の名誉毀損罪は構成要件上、公然と行われる必要があるが、民法上はそのような条件は特に置かれていないため、公然性は要件とならないと解される(同頁)。
名誉毀損の免責要件については、有名な最高裁判例がある(最判昭41・6・23)。それによれば、問題とされた表現が、公共の利害に関する事実にかかり、もっぱら公益を図る目的に出た場合には、適示された事実が真実であることが証明されたときは、違法性がなく、不法行為は成立しない。仮に真実であることが証明されなくても、行為者において「その事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である」とされている(41頁)。
このように、表現が公共目的をもったものである場合は、たとえ真実であること自体の証明ができなくとも、真実であると信じたことに相当の理由があれば免責されることになる(72頁)。相当性の要件の有無によって裁判の勝敗が決まることもあるということである。例えば、しばしば問題になる新聞、週刊誌、テレビ等のマスメディアによる名誉侵害については、「情報として適示した事実に関する取材の範囲・方法・内容が問題になることが多い」とされる(同頁)。
この場合、被告とされたマスメディアが、自分の相当性を立証するためには、取材源、取材の範囲・経緯、取材の方法・内容等の事情を具体的に明らかにすることが重要である(73頁)。
例えば、新聞記者Aが、ある人物Bから、他人Cがオレオレ詐欺の主犯格であるとの話を聞き、それをそのまま鵜呑みにして、実は何ら犯罪に関与していないC氏について、「C氏はオレオレ詐欺グループのリーダーである可能性が濃厚」という記事を出した場合、C氏に対する名誉毀損行為が成立する(なお、虚偽の話をしたBも共同不法行為責任を問われる可能性がある。また、Bのような人間に限って、自分の身に危険が及ぶと、そのようなことをAに話した覚えは一切ないと否定し、逃げてしまうのが普通である。)。
この場合、記者Aとしては記事を書く前に、最低限、対象者であるCにも取材を申し込み、Cの言い分も確認する必要があったことはもちろん、Bと利害関係を持たない第三者Dにも取材をかけ、本当にBが言っているような事実があったかどうかを慎重に吟味する必要があった。つまり、裏付けをとる必要があったということである。十分な証拠をそろえた上で、「ほぼ間違いない」と確信して発表した場合に限って相当性(免責事由)が認められる場合があるということである。
升田氏は、被害者が加害者の責任を追及しようと訴訟を提起した場合、非常に重要なポイントを指摘されている。それは、名誉毀損を行う者は、一部の例外を除き、「特定の動機・目的の下、特定の方向で被害者を誹謗中傷しようとするものであり、文書の記載も、放送も、発言も、これらの意思に従って行われているものであるから、・・・記載等の全体が名誉毀損等の意思に従って構成されることを重視した主張・立証を展開することが重要である」との箇所である(101頁)。要するに、加害者の全体的意図を裁判官に十分に理解してもらうことが大事だということである。
升田氏も言っておられるが、名誉毀損のトラブルは、「誰でも、いつでも、どこでも被害者になり得るし、加害者にもなり得る」(5頁)。特に法律を専門とする弁護士の場合、自戒の念を込め、日頃から無用のトラブルに巻き込まれないよう脇を固めておく必要があろう。

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.