
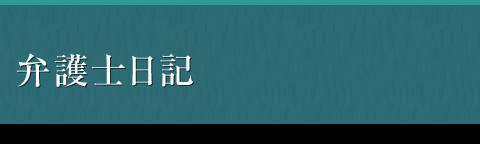
本屋でたまたま上記の本が目にとまり、さっそく購入した。クラウゼヴィッツが書いた「戦争論」は、戦争を考える上での必読書ないし古典とされてきた。しかし、その内容は体系的ではなく、難解であるという話も聞いていた。そのため、これまで購入していなかった。
しかし、今回の本は、日経ビジネス人文庫の1冊であり、総頁数も300頁を下回っている。2~3日もあれば完全に熟読することが可能なコンパクトな本である。本書によれば、クラウゼヴィッツは、1780年生まれのプロイセン王国の軍人である。彼は、プロイセン王国とフランス(ナポレオン)との戦争に従事し、一時フランス軍の捕虜となった経験もあるという。ところが、クラウゼヴィッツは、戦争論を執筆中の1831年にコレラに罹患し、51歳の若さで亡くなったようである(84頁)。
加藤氏の編訳にかかる本書は、「戦争論」の中の示唆に富む記述を、短い文書で適示しており、要点を掴むのには最適である。今回は、たまたま狂気の侵略者ロシア(プーチン)によるウクライナへの無差別攻撃という格好のお手本が現実に示されている。そのため、本に書かれた重要ポイント(理論)と現実に起こっていることを対比しながら、自分の頭で考えることができる。
本書には極めて有益な見解が示されているが、特に、印象に残った点を掲げてみたい。
まず、「戦争とは、異なる手段をもって継続される政治である」。クラウゼヴィッツによれば、戦争とは、政治的手段とは異なる手段をもって継続される政治であるという(37頁)。戦争=政治という視点である。また、彼は、「戦争は、相手に自らの意思を強制するものである」という(38頁)。戦争とは、相手に自分の意思を無理やり受け入れさせるものである。今回、侵略者ロシアのプーチンの行動もこれに沿ったものと言い得る。ウクライナに対し、「ロシアの言う事を聞け」という姿勢である。
また、政治と戦争の関係について、彼は、「政治が戦争を生み出す以上、戦争は政治の手段であり、決して逆ではない」ともいう(77頁)。今回の侵略者ロシアの独裁者プーチンが仕掛けた戦争も、やはり政治的な意図をもって始まったものといえよう。
我が国では、来月参議院議員選挙がある。各党の候補者を見ていると、どうしてこのような平々凡々たる人物ばかりなのかと嘆息するほかない。特に「平和憲法の護持」を掲げる左翼勢力の連中には、健全な国防意識が欠けているとしか思えない。クラウゼヴィッツは言う。「流血を厭う者は、それを厭わない者によって必ず圧倒される」と(87頁)。流血を厭わずに力を行使する者と、その行使をためらう者とでは、行使する方が優勢を得ることは間違いないということである。そして彼は続けていう。「流血をただ怖がっていると、するどい剣を持っている者が現れ、やられてしまう」と(97頁)。国政を担おうとする者が、「平和憲法」という意味不明の呪文を1万回唱えても、戦争を防止する上では全く効果がない。日頃から防衛力を強化し、敵(中・露・北)に対し「日本に手を出したら、ただでは済まないぞ」と警告しておくことが重要だということである。
クラウゼヴィッツは、防衛の在り方について、「防御して反撃しない者は滅びる」という(233頁)。やや詳しくいえば、防御を最終の目的と考えるのは、戦争の概念と相いれない間違った考え方であり、戦争の方法として敵を迎撃するだけに限定し、全く反撃しないのは無意味であるという。この結論は、普通の知能をもって冷静に考えればごく当たり前のことといえよう。
また、軍事同盟について、クラウゼヴィッツは、「無能卑屈で防御一辺倒なら、他国に支援されず、没落する」と述べる(270頁)。彼は、実例として、18世紀にポーランドが、プロイセン、ロシア、オーストリアの3カ国によって分割されてしまった例を挙げる。
日本も、メイドインUSAの欠陥憲法をすみやかに改正し、まともな防衛意思を掲げた正常な国に生まれ変わる必要がある。ここで、日本の防衛にとっては日米安保条約が重要な意義を持つが、クラウゼヴィッツは、「他国の危機に際し、同盟国は自国のことのように真剣にはならない」と警告している(273頁)。したがって、日本は、他国(アメリカ)頼みでは駄目であり、日本だけで防衛と敵に対する攻撃(反撃)ができる十分な手段を確保する必要がある。
日頃、(私個人からみて)不見識な社説をしばしば掲載する新聞がある。地元の岐阜新聞である。社説を書いているのは共同通信の人間だと聞く。不見識な記事のポイントは、いつも変わっていない。一つは「軍拡競争」というワードである。二つ目は「対話」ないし「対話外交」である。
最初の「軍拡競争」という言葉であるが、この記事を書いている人物は、今まで社説上で「軍拡競争」の定義を詳細に明らかにしたことはない。一体どういう意味で使っているのか?世界の各国が自国の防衛のために軍事力を整備し、自国民の安全・安心を確保しようとすることがなぜいけないのか?そのようなまともな国家の行動を取り上げて、なぜ悪いイメージがある「軍拡競争」と勝手に命名しているのか?その説明がない。
また、中国の急激な軍事予算の拡大をどう認識しているのか?これを受けて日本が防衛費を相応の程度増額することが、換言すると、GDP比2パーセント程度まで僅かに増額することがなぜ日本(国民)にとってマイナスとなるのか?その説明がない。深読みすると、日本が防衛費を増額すると中国共産党にとっては明らかに不利となる。そのような状況は、戦略上回避したいという隠された意図があるのか?
二つ目の「対話外交」であるが、記事を書いた人物は、「対話」という言葉をどのように定義するのか?対話とは、少なくとも共通の価値観(理念)を持った者同士でしか成立しないのではないのか?問答無用とばかりに、力ずくで隣国を攻撃しようとするロシアのような専制国(全体主義国家)とは、そもそも対話など成り立たないというべきである。仮に会談しても、見解の不一致の確認(又は非難の応酬)しか生じないのではないのか。安易に「対話」というワードを頻繁に使っている点は、やはり疑問である。間違った意見を「新聞」という公共性の高いメディアに堂々と記載していることによる弊害は、決して無視できない。
現実社会に目を戻すと、依然として犯罪者プーチンによるウクライナへの違法な攻撃が続いている。私の予想では、2022年末に至っても戦争は終結していないと見る。ともかく戦争をまともに終結させるためには、侵略者ロシアが完全に敗北すること以外に良い方法はない。プーチンという悪魔がこの世から早く抹殺されることを願うだけである。
私は農地法を長年にわたって勉強している。農地法についての解説書は、私がいろいろな解説書を出す以前は、昔、全国農業会議所という法人が出している本でほぼ独占されてきた。
今でもこの法人から農業関係の解説書が出ており、私も時折参考にしている。今回私が問題とするのは、農地法3条3項1号である。この条文について、農水省は法的に間違った解釈を示しており、未だに訂正しようとしない。非常に頑迷である。よく考えると、これはとんでもないことである。農水省は国家の行政官庁の一つであり、言うまでもないが、建前としては、国民に対し正しい法律解釈を示す職務上の責務があるからである。
この誤謬は、弁護士、裁判官または検察官という資格を持った法律家であれば、容易に発見できるミスである(仮に発見できなければ余程のぼんくらであろう。)。しかし、そもそも農地法3条の条文を詳しく読み込んだ法律家は余りいないであろう。そのため、ミスを発見する人もほとんどおらず、結果、批判する声も大きくならず、長年にわたって見過ごされてきたのである。おそらく農水省の現時点の担当職員は、実は法的にみて問題のある表現であることが分かっているのであるが、先輩職員がやってしまった事務的ミスを自分の時代に的確に指摘することに大きな心理的抵抗感があるのではなかろうか。
法人の場合、農地の所有権を取得しようとしても、農地法2条3項の要件を満たした農地所有適格法人でないと認められない。つまり、農地法3条1項の許可が下りない。ところが、農地法3条3項を使えば、上記原則の例外として、一般法人であっても農地の権利を取得できる。ただし、取得できる権利は、賃借権又は使用貸借による権利に限定される。
ここで、農地法3条3項柱書を呈示する。「農業委員会は、農地(・・・)について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、(・・・)第1項の許可をすることができる」と書かれている。農地法3条3項には3つの号があるが、理解を容易にするため、3項2号と3号は要件をクリアーしているという前提とする。そうすると、残るのは1号である。3項1号は、「これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地(・・・)を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること」と定める。
この条文の解釈は、例えば、農地甲の所有者であり賃貸人であるAと、当該農地甲の賃借人である法人Bが、農地甲について賃貸借契約を締結し、農業委員会で許可も受けたが、後日、賃借人である法人Bが農地甲の耕作を止めてしまい、荒れ放題の状況を呈している場合、賃貸人Aは賃貸借契約を解除できるということである。つまり、「適正に利用されていないと認められる場合」には賃貸人Aとしては解除権を行使できる旨を当初の契約で明記したということである。そうすると、普通の法律家であれば、このような文言を契約書に盛り込むことで、信義に反する行為をした賃借人Bとの契約関係を容易に断ち切ることを狙ったものであることが分かる。そうすると、この条項は、約定解除権の付与であり、解除特約の一種であるという理解に到達する。
ところが、農水省の職員には民法の基本的知識が欠如しているためか、このような契約をもって「解除条件付き賃貸借」と称し、かつ、パンフレットまで作成した上で全国の農業委員会の職員に対し「そのように理解されたい」と宣伝を行っている。そのため、一部の関係者は思考停止状態に陥り、農水省が「白い猫」と言えば、現実には黒い猫であっても、異口同音に「白い猫です」と恭順の意思を示している。その姿にはプライドというものが全く感じられない。実に卑屈な態度と言い得る。
なぜ、農水省の解釈が、「フェイク解釈」に当たるのかと言えば、民法127条2項には「解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う」と明記されているからである。民法の言う解除条件とは、ある条件が成就することによって契約の効力が直ちに消滅するものを指す。
そうすると、農水省の言う「解除条件付き賃貸借」の「解除条件」という文言と、民法127条2項の「解除条件」という文言との相互関係が問題となる。仮に農水省の職員が、双方の文言の法律的な意味を同一と理解していた場合、賃借人Bによる農地甲の「不適正利用」の事実が認定された途端に、何らの意思表示も不要でAB間の賃貸借契約も当然に消滅することになる。しかし、このようなおかしな解釈は、農水省であっても採用していないであろう。なぜなら、農水省の立場に立っても、賃貸人Aから賃借人Bに対する解除の意思表示は必要とされているからである。
このように分析した場合、間違いの根本原因は、昔の農水省の担当職員が、農地法3条3項1号について、能天気に「解除条件付き賃貸借」と呼んでしまったことにある。しかし、世間に対し、誤解を与えないようにするには、「解除条件付き賃貸借」という呼び方を正式に廃止し、今後は、「解除する旨の条件が付いた賃貸借」あるいは「解除特約付き賃貸借」とでも呼ぶほかないであろう。

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.