
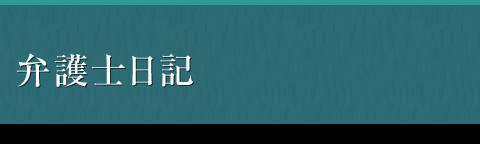
1 Aが所有する農地甲があり、その農地の賃借人Bが遺言を作成しようと考えた場合、大きく分けて「相続させる」遺言と「遺贈する」遺言の二つが考えられる。そこで、これらの遺言について何か違いがあるのか否か検討する。
まず、相続させる遺言であるが、遺言で受益する者は相続人に限定される。非相続人が指定されることは想定できない。そして、相続させる遺言には二通りのものがあり、受益相続人が相続する財産が特定されている場合と、特定されていない場合である。
前者は、民法上は特定財産承継遺言と呼ばれる(民1014条2項)。例えば、Bの所有する土地・建物を相続人の一人であるCに相続させる場合がこれに当たる。相続が開始つまりBが死亡すると同時に、当然に土地・建物の所有権はCに移転する。相続人間で遺産分割の手続を踏む必要はない(民906条)。登記手続は、Cの単独申請で足りると解される。
一方、後者は、相続される財産が特定されていない。ではどのような場合に生じるかと言えば、Bが相続分の指定をした場合である。例えば、Bの相続人として、長男C及び次男Dの二人が存在していたところ、「Cに3分の2を、Dに3分の1を相続させる」と遺言した場合がこれに当たる。この場合、具体的にどの遺産が誰に相続されるのかは遺言だけでは明確ではない。そのため、後日、遺産分割協議を行って遺産の帰属を確定させる必要がある。
2 このようにBによって相続分の指定が行われ、Bが死亡したものの未だ遺産分割の手続が完了していない場合、生前Bが有していた賃借権(耕作権)は誰に帰属することになるか。農地甲について存在する賃借権もまた一種の財産権である。そして、賃借権は債権であり、共同所有の状態に置かれていると解されるが、このような状態は準共有と呼ばれる(物の共有ではなく、権利の共有であるため準共有となる。)。つまり、C及びDは、被相続人Bが生前に保有していた賃借権を共同で承継した状態にあるということである。
この場合、C又はDは、どの範囲で農地甲を耕作することができるのかという問題がある。この点に関しては、最高裁判例は、遺産共有も通常の物権法上の共有と性質を異にするものではないとの立場をとっていることから(最判昭30・5・31)、通常の共有と同様に解すれば足りる。すなわち、民法249条によって、各共有者は、共有物の全部についてその持分に応じた使用をすることが認められる。
上記の事例の場合、C又はDは、平等に農地甲の全部について耕作する権利がある。ただし、持分による制限はあると解されるので、仮にCが農地甲の全部を耕作した場合、特にDがそれを了解していたような場合を除き、Dから、Cに対し同人の持分を超えた部分の使用について使用料の支払い要求があったときは、これに応じる義務があると解される(最判平12・4・7)。
では、C又はDは、自分たちが共有する賃借権を、他人Eに譲渡することができるであろうか。結論を先に言えば、賃貸人Aの同意がない限り、賃借権を勝手に譲渡することはできない。そのことは、民法612条1項の規定から明らかである。
3 次に、農地甲の賃貸人Aは、誰に対し賃貸料(小作料)を請求することができるか、という問題がある。これはC及びDの側から見た場合、賃借料をどのような割合で負担するかという問題である。最高裁判例は、賃料債務のような可分債務は、法定相続人の相続分に従って承継されるとしているため(最判昭34・6・19)、C及びDに対し半額ずつ請求することができると解される。
なお、CとDが遺産分割を行って、例えば、土地と建物の所有権はCが取得し、他方、農地甲の賃借権はDが取得するというように話がまとまった場合、以後、賃借料全額の支払いはD一人が行うことになる。
4 次に、遺贈である。遺贈によって財産をもらうことができる者を受遺者という。遺贈の場合、相続人の場合はもちろんのこと、非相続人であっても受遺者となり得る。また、法人であってもかまわないとされる。遺贈には、遺贈の目的物が特定されている特定遺贈のほかに、目的物が特定されない包括遺贈というものがある(民964条)。包括遺贈は、さらに全部包括遺贈と割合的包括遺贈に分類される。そして、包括遺贈を受けた者を包括受遺者という。
割合的包括遺贈とは、相続財産の分数的割合による遺贈であり、例えば、Bが「他人Fに対し相続財産の3分の2を遺贈する」と遺言したような場合である(他方、「Fに対し相続財産の全部を遺贈する」と遺言したような場合は、全部包括遺贈となる。)。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(民990条)。あたかも相続人と同じような立場に置かれ、相続の承認・放棄の規定が適用される(民915条)。仮に上記の事例で、Fが遺贈を拒否したいと考える場合は、それを放棄することも可能である。
なお、Bが例えば、「Fに対し相続財産の3分の2を遺贈する」と遺言した場合、Fは本来の相続人C及びDと共に、遺産分割の当事者として分割協議に参加することが認められる。遺産分割の結果、仮にFが土地と建物の所有権を取得することになった場合、移転登記手続は、登記権利者Fと登記義務者である相続人C・Dとの共同申請となる。

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.