
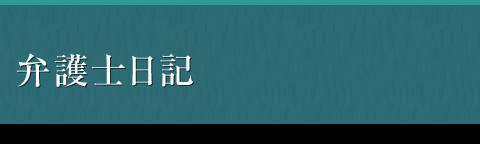
私が執筆した「農地法読本」の全訂版が2025年11月下旬に大成出版社から発売される。
農地法読本は、初めて2011年10月5日に初版が出た。その後、数年に一回程度の改訂があり、2021年㋅30日に第6版を出した。その後、本の在庫がなくなってきたため、出版社の方から、改訂作業をお願いするとの意向が2024年の秋に示された。
そこで、私は、2024年の秋に執筆計画を立て、2025年の1月から5月までに原稿を書き上げるスケジュールを立案した。ただし、7訂版とするのでは内容に目新しさがなく、多くの読者の期待に添えないと考えた。そこで、従来の本の内容を根底から練り直し、全く新しい原稿を一から執筆することとした。2025年の1月から5月までかかって、約280頁分の原稿を作成し、東京の大成出版社へ郵送した。なぜ、5月末日に締め切り日を置いたのかといえば、6月4日から同月13日までトルコへ観光旅行をする計画を立てていたからである。
6月13日に帰国してから、しばらく休養し、6下旬からは送られてきたゲラ刷りの校正(一校)作業に入った。その後、校正作業は3回続いた。通常、校正は2回で済む。しかし、今回は全ページにわたって新規に原稿を書いたことから、校正すべき箇所が多く見つかった。そのため、例外的に計3回の校正となったものである。
今回の本は、第1章「総論」、第2章「耕作目的の農地の権利移動」、第3章「農地の転用等」、第4章「その他の諸問題」という構成になっている。解説部分は279頁までであり、これに付録の条文などが付く。詳細な事項索引が付いているため、何か調べたい事項が生じた場合、すぐに該当ページを開くことができる。また、判例索引も付いている。
ここで、今回の私の本の狙いを示す。一般論としていえば、著者が本を執筆した狙いないし目的と、その本を購入した読者の意図ないし目的が一致すれば、読者は、本に満足する可能性が高いと言い得る。反対に、双方の意図に食い違いがあるときは、読者は不満を感じる(本に対する事後評価は低くなる)。
ただし、本の著者が、あらかじめ多くの読者の希望を聞いて、本の執筆にとりかかることは皆無に近いであろう。通常は、著者が自分だけで判断して本の内容(執筆内容)を決めていると思われる(編集者の意見を事前に聴くことはあり得るが、自分の場合は、編集者から内容について特に注文が出たことはなかったと記憶する)。
以上のことから、もっぱら本を購入する読者の方で、事前に本の内容をある程度把握し、その内容に納得して本を購入することが、失敗を回避するためには重要ということになる。
今回の農地法読本[全訂版]は、あくまで法律書である。つまり、法律を解説した本である。しかも、農地法という法律は難解であり、行政法と民法の知識がないと正確に理解することができない。そのため、行政法と民法の基礎的知識が解説されている。よって、書店に多く並んでいるいわゆる「QアンドA」形式の本ではない。
また、この本には、例えば「どのような申請書を作成して提出したら、うまく転用許可が得られるか」、「許可申請書に添付すべき書面は何か」というような細かい技術的事項は解説されていない。思うに、同じ「士業」であっても、弁護士にとって関心があるのは、行政機関の行った処分または行為が違法か違法でないかのみである。他方、行政書士、税理士、司法書士のような、如何にしたら申請(申告)をお役所でトラブルなく受け付けてもらえるのかという問題意識は、(そもそも最初から業務として申請または申告することがないため)、全くない。弁護士の主たる業務である訴訟には必ず相手方がおり、判決を通じて勝敗が決まる(ただし、和解で解決することもある。いわば「引き分け」である)。
それに対し、これらの3つの士業の場合、申請(申告)を認めてもらう相手方は、一般の行政機関であり、税務署であり、法務局である。したがって、これらのお役所(例 農業委員会)が適正と認める形式および内容の書類を作成し、無用に争うことなく円滑に申請・申告をスムーズに処理してもらうことが重要と言えるのではなかろうか。
したがって、これらの士業に就いている方々が本書を仕事用に購入しても、一部の純粋に勉強好きな方々を除き、余り役に立たないであろう。お役所の担当者から言われたとおり、書式を整え、かつ、必要な書面を添付して提出し、審査に通れば、それで仕事としては合格点が付くのである。何もわざわざ貴重な時間を割いて農地法・民法・行政法の勉強をする必要はないと言える。
もっとも、法的教養を高めるためにあえて勉強したいという意欲のある方が、時間を捻出して勉強することは好ましいことであり、大いに推奨できる。そのような次第であるから、著者としては、弁護士を除く普通の士業の方々には、この本は積極的にお薦めしない。仮に購入して読まれても「一体何のための本だったのか?」、「4400円損した」とがっかりされることになるかもしれないからである。
このように弁護士の場合、そもそも行政機関と協調して業務を行うという発想がない。そうではなく、行政機関の違法・不当な行為があるか否かを監視し、仮にあった場合は、それを指摘し、是正を求め、場合によっては提訴することを通じ法的責任を追及するという手法をとる。いわば、闘争スタイルが基本である。
したがって、闘争に勝利し、弁護士としての職責を十分に果たし、依頼者に満足してもらうためには、農地法、行政法および民法の基礎的知識が必須となるのである。法律論に通暁することが成功のカギとなるのである、今回の本も、その点に主眼を置いている。
著者としては、極力、平明に解説しているつもりであるが、内容自体は簡単なものではないため、自分の頭を使ってしっかりと考え、かつ、理解し、更に記憶する必要がある。間違っても、ソファーの上に寝転んでページをぱらぱらとめくれば本の内容がよく分かるという代物ではない。
しかし、弁護士の場合、普通に考えても法律的知識は相当程度あるはずである。弁護士登録の前に司法試験に合格し、かつ、司法研修所(中で1年間の司法修習を受ける。昔は2年間だった)を卒業していることから、その気(本気)になれば、骨格部分は半年程度で完全マスターできよう。ただし、農地法の条文の細部まで正確に理解・記憶しようとすると、1年以上はかかるのではなかろうか。
ただし、一方で、行政機関に勤務する公務員には法律論の学習は不要ということにはならない。第一、「法律による行政」を遂行する職務上の責任があるからである。したがって、担当公務員としては、何をしたら違法・不当になるのかを事前によく勉強しておくことが非常に重要となる。公務員が公務(特に許認可事務)を遂行するに当たって、先例と古い知識を基に、仮に漫然と事務を処理した結果、相手方から勤務している行政主体が訴えられるようなことになれば、非常に面倒なことになる。場合によっては、人事評価上、担当公務員に大きなマイナス点が付くおそれもある。したがって、都道府県、市町村の農地法担当者が、この本を読んで一定レベル以上の法的知識を涵養しておくことには大きな意味があると考える。
この本の購入を検討している方々は、以上の点に留意され、購入するか否かを慎重に検討されたい。
(追記2025.11.30)
2日前に、仕事で名古屋へ行く機会があり、帰る途中、名古屋市の繁華街である栄の「丸善」に立ち寄った。農地法読本[全訂版]も確かに書棚に置いてあった。しかし、この本が置いてある場所は、「農業一般」のコーナーであった。そこに並べてあるその他の大半の本は、大学の農学部の教員あるいは農業者(又は農業技術の専門家)が書いたと思われる本で占められていた。丸善のスタッフは、農地法読本[全訂版]が、純然たる法律書解説書であることが全く分かっていない。タイトルに「農地」という表示があるから農業書の一種に違いないと誤解しているのであろうか?しかし、農業者には、農地法読本[全訂版]は、ほぼ無用である。本の販売を専門の仕事とする大きな書店ですら、この程度の認識しかないのは残念と言うほかない。

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.