
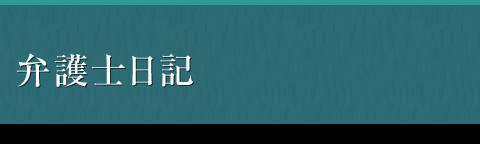
1 弁護士法72条は、弁護士資格を有しない者(非弁護士)による法律事務の取扱いを禁止している。この規定は、弁護士の資格を持たない者が、報酬を得る目的で、かつ、業として訴訟事件その他一般の法律事件に関し、鑑定、代理等を行うことを禁止している。この規定に違反すると、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる(弁護士法77条)。
2 立法趣旨は次のようなことである。弁護士として職務を行うためには、原則として、高度の法律知識を要する司法試験に合格する必要があり、また、入会を許された所属弁護士会による規律を受けるなど厳格な行動規範が定められている。これは、基本的人権の擁護及び社会正義の実現という高度の職務を果たすための最低限の条件である。
ところが、そのような能力と規律を受けない一般人が、仮に弁護士業務を自由に取り扱うことができるとされれば、社会的な安定を損ない、また、法的秩序を著しく乱すことになりかねない。ちょうど、医師免許を持たない者(ニセ医者)が医療行為に従事するようなものである。そこで、弁護士法は、他人の法律事務に介入する資格を持つ者を厳しく制限している。
ただし、弁護士法以外の法律によって取扱いを認められている法律事務については、その法律の定めるところによる。例えば、司法書士は、他人を代理して登記申請書を有償で作成することができるし、また、作成した申請書を代理人として法務局に提出することもできる。さらに、認定司法書士の場合は、訴額140万円を超えない簡易裁判所の民事訴訟事件について、他人の代理人となることが認められている。
3 弁護士法72条によれば、一般の法律事件について、例えば、鑑定することが原則として禁止される。ここでいう「鑑定」とは、法律事件について法律的な観点から意見を述べることである。例えば、Aという人物が友人Bに金300万円を貸したが、Bが返済期限になってもお金を返済しようとしない場合に、困ったAが、弁護士Cに対し、お金を取り戻すための法的方法を尋ねるような場合がこれに当たる。いわゆる有料法律相談である。
仮にAが弁護士資格を持たないDに対し法律相談を依頼し、これに対しDが有料で回答したような場合は、Dの行為は、いわゆる「非弁行為」に該当し、違法となる可能性がある。可能性があるとした理由は、Dの行為が「業として行った」ものとは言い難い場合には、つまり反復継続して行うものではないと認められる場合は、非弁行為には当たらないと解されるためである。また、例えば、法学部の学生が、一般市民を対象として定期的に大学の構内で「無料法律相談」を行うこともある。このような定期的な法律相談会の場合、反復継続が予定されていることはそのとおりであるが、しかし、学生による相談会は完全無償であって報酬を得る目的を欠くため、非弁行為には当たらないと解される。
4 では、有料のセミナーにおいて、講師が法律の解説を行うことには問題がないであろうか?法律の解説といっても、具体的な法律問題ではなく、あくまで事例として解説するのであれば問題ないと言える。大学において法学部の教授が、学生に対し授業を行う際に、過去に発生した事件に関する具体的な判例を取り上げて法的評価を交えて解説するのと同じであり、問題ないであろう。
5 では、弁護士資格を持たない講師が、農地法のセミナーを行ったが、セミナーの中で、受講者の方から「今、私の自治体では、かくかくしかじかの問題が起きて苦慮していますが、どう対処するのが正解か、ここで講師の法的見解を示してください」と質問された場合は、気を付けなければならない。なぜなら、そのような質問は、具体的な法律事件(ここでいう「事件」に該当するためには、別に訴訟や調停にまで発展している必要はない。)に関するものであり、しかも、講師の法的見解を問うているからである。その場で講師が答えれば、それは法的見解を開示したということになり、弁護士法72条の「鑑定」に当たることになると解される。講師が弁護士資格を持っていれば、最初から問題となる余地がない。
しかし、例えば、講師が行政書士の資格しか持っていないような場合、行政書士は鑑定を行う法的資格がないため、いわば素人が法的見解を述べたことになる。しかも、セミナーが有料参加の場合、講師も主催者から所定の講師料を受け取っているのが普通であり、「報酬を得る目的」があったと認定できる。また、セミナーの性格として、受講生から出た同様の質問には原則として回答を行うものとするという方針が示されている場合は、当初から反復継続が予定されているため「業として」行っていると解することができる。
6 以上のことから、セミナーを運営する主体(主催者)は、弁護士以外の者が講師となって法律問題を扱うセミナーを開催する場合は、後になってから「まさか責任を追及されるとは考えてもみなかった」というようなコメントを出すことがないよう、慎重に準備する必要があろう。
1 本日(2022年5月17日)付けの岐阜新聞の記事によれば、昨日、岐阜地裁は、産廃施設許可を取り消すという判決を下したと報道されている。事案の内容はやや複雑であり、仮に弁護士資格があっても、記事内容だけを材料にして短時間で判決の是非を正確に理解することは容易ではないと思われる。そこで、さっそく解説を行う(ただし、手元の資料は上記新聞記事のみであるため評価の正確性には一定の限界があることをお断りする。)。
2 事の発端は、岐阜県が、2009年の11月に岐阜県中津川市内における産業廃棄物処理施設の建設計画について許可処分を行ったことにある。ところが、県は、許可申請者(業者)の説明に誤りがあったという理由で、2010年4月に上記許可処分を取り消した。申請内容に事実と違う点があったので、職権を発動して許可を取り消したというのである(職権取消し)。
そうすると、そもそも許可時点において瑕疵(違法又は不当な事由)があった可能性が高いと言い得る。職権取消しという行政の自己反省のための仕組みは、もちろん重要な制度であるが、しかし、その実例は余りないのではなかろうか?したがって、2009年に出された許可処分自体が非常にいい加減なものであった可能性がある。平易な言葉でいえば、担当職員が平均的な法律知識のレベルに達していなかったため、安易に許可処分を出したのではないかという疑いが残る(古田知事の下、岐阜県職員採用試験において、昔のように専門知識を尊重・重視せず、「人物本位」という耳障りのよい時代迎合的な採点方法が影響しているのかもしれない。)。
3 上記のとおり、2009年に県がいったんは出した許可を、県自らが2010年になって職権を発動して取り消した。そのことによって、当該許可処分は最初からなかったことになる(白紙、つまり申請時の状態に戻る。)。ところが、申請者(業者)はこれ(つまり取消行為)を不服として行政不服申立てを環境大臣に対して行った。その結果、2013年12月、環境大臣は、上記の取消行為(なお、上記記事では撤回と表示されている。)を取り消した。その結果、法律的には許可処分が存在する状態に戻る。
しかし、この環境大臣による裁決を不服として、地元住民は、右裁決の取り消しを求めて訴訟を提起したが、結局、2019年3月に住民側の敗訴が最高裁で確定した。その結果、環境大臣の行った上記裁決は適法ということが確定する。その結果、上記のとおり岐阜県知事による申請者(業者)に対する許可処分は有効という状態が未来永劫継続することになる。
4 そこで、住民側は、岐阜県を被告として上記許可処分の取消しを求める行政訴訟(取消訴訟)を提起した。今回、岐阜地裁の鳥居俊一裁判長はこれを認め、住民側が勝訴した。
しかし、この判決には、次のような疑問点がある。取消訴訟の訴訟要件という問題である。訴訟要件とは、適法に取消訴訟を提起し、裁判として系属するための要件である。訴訟要件が一つでも欠けると、却下判決となる(原告敗訴)。
その訴訟要件の一つとして、狭義の「訴えの利益」というものがある。換言すると、訴訟の提起及び係属中において、岐阜県知事の上記許可処分を取り消す現実的必要性があることが要件とされる。例えば、違法建築物に対する除却命令が出され、代執行に基づく建物除却工事が完了してしまった場合、除却命令の取消しを求める訴えの利益は失われる、というのが昭和48年3月6日の最高裁の判例である(宇賀克也「行政法概説Ⅱ第6版」216頁参照)。
5 上記新聞記事によれば、「施設は着工されず、予定地は他の業者に売却され、現在は太陽光パネルが設置されている」と言う。一般論として、通常の許可処分とは禁止の解除である。国の法律によって一定の行為を行うことが原則禁止される状態に置かれるが、申請者が個別に許可申請をすることによって、当該法律の定める要件を満たした場合は、許可処分が出て法律による禁止が解除され、自由に活動することが許される。産廃施設についていえば、どこに設置するかという立地条件が、許可処分をするための重要点となっていることは疑いない(対物許可)。
6 そうすると、許可を受けた土地は、現時点では他人の所有物となっているのであるから、最初に許可処分を受けた業者が、少なくとも現在の所有者から当該土地を買い戻すことに成功しない限り、単に、許可書が手元にあったとしても、その地に産廃施設を建設することは不可能という以外にない。そうすると、訴えの利益はもはや存在せず、却下という判決も十分にあり得たのではないかと考えることも可能である(仮に岐阜県が控訴した場合、名古屋高裁の裁判官がそのような立場をとる可能性がある。)。
7 より深く考えると、岐阜県としては、提訴の前に、有名無実となった許可処分を撤回しておけばよかったとも言い得る(ただし、岐阜県知事は、環境大臣による裁決の結果に拘束されるから、撤回処分をすること自体が許されないという議論がある。)。撤回処分は、許可後に新たに生じた事由を根拠として、もはや許可処分をそのままにしておく理由が無くなった場合に行い得る(職権による撤回処分)。処分を撤回しておけば、住民側が訴訟を起こすことを未然に防止することもできたのである(結果、無駄な弁護士費用も発生しなかった。)。
しかし、年季が入った古田知事の率いる岐阜県の担当者には、そのような知恵は働かなかったようである。事なかれ主義である。そのような現象が起きる原因はいろいろとあるが、一つは、執務上必要とされる法律の基本知識が欠如していることではなかろうか(何か分からないことがあったら、自分で追究するのではなく、その都度東京の霞が関の役人にお伺いを立てれば十分であるという思考停止的な考え方に陥っていた可能性がある。)。今後は、地方公務員たる者、自分の頭だけで適正な判断ができるための法律知識を涵養する必要があろう。岐阜県としても、より多くの予算と時間を割いて県庁内における法律研修を充実させる必要がある。
(追記)
2022年5月21日付けの岐阜新聞を読んでいたら、「中津川の産廃処理施設訴訟」について「県が控訴せず」という見出しが出ていた。記事によれば、古田知事は「当該企業は既に清算されており、本件処分を維持する意味がないため、控訴しないこととした」という見解を述べた。これにはやや驚いた。なぜか?通常、行政が被告とされた行政訴訟においては、仮に一審で負けても、ほぼ全てのケースで控訴して争うのが普通だからである。ところが、今回は一審で負けたがそれで良しという姿勢である。極めて異例の対応である。これは推測であるが、岐阜県の幹部職員は、住民が訴訟を提起した当初から、「この訴訟には負けても仕方がない」と考えていたのではなかろうか?そのように推理しないと辻褄が合わない。前記のとおり、岐阜県は、この「政治案件」に対し関心を払い、もっと早い時期に職権を発動して許可処分を取り消しておくべきであった。そのように適切に対処しておれば、今回の訴訟を招くこともなかったのである。これは古田知事の判断ミスと言えよう。

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.