
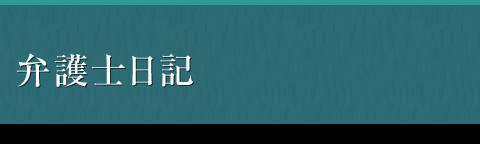
交通事故によって被害者に損害などが発生した場合、被害者は、加害者に対し損害賠償の請求を求めることになる。その場合、よく問題になるのが過失相殺という概念である。過失相殺とは、公平の観点から認められるものである。つまり、事故の発生について被害者にも落度がある場合に、被害者の落度に応じて賠償金額が減額されるという仕組みである。ただし、過失相殺をするか否かは、裁判官の裁量に委ねられており、裁量権の範囲内における判断については、双方の当事者とも異議を出すことはできない。
さて、名古屋地方裁判所は、平成28年2月26日、次のような判決を出した(交民49巻1号288頁)。
この事故は、名古屋市中川区富田町で発生した。東西道路を西から東に向けて走行していた車両(優先車両A)と、交差する南北の道路を南に向けて走行していた車両(非優先車両B)が、交差点で衝突したというものである。
この道路は、Aが走行していた方が優先道路となっていた。つまり、東西の道路は、中央線により区分された片側1車線の道路であった。他方、Bが走行していた南北の道路は、そうではなく非優先道路となっていた。
ここで、双方に不注意があって、Aの車両とBの車両が交差点内で衝突事故を起こしたのである。原告Aの主張とは、被告Bは全く右方向を確認することなく原告運転の被害車両が走行する幹線道路に突然進入してきたのであるから、被告には著しい過失があり、他方、原告には何らの過失もないから、過失相殺をすべきでないと主張した。
これに対し、被告は、自分は一時停止の上で本件交差点に進入した。事故態様から原告にも10%の過失相殺を行うべきであると答弁した。
双方の主張をまとめてみると、原告の方は、原告には過失はないとの主張であり、かたや被告の方は、原告にも10%の過失を行うべきであるという主張であった。
これら双方の主張を踏まえ、名古屋地裁は、次のように判決した。
そもそも、被告Bは、優先道路を通行する原告車Aの通行を妨害してはならない義務がある(道交法36条2項・4項)。にもかかわらず、右方の安全確認不十分のまま漫然と本件道路に進入して本件事故を引き起こしており、その過失の程度は大きい。
一方、原告Aも、本件道路の交差点の手前で被告車Bが一時停止中であり、しかも、被告Bは原告Aの側を見ていないことに気が付いたのであるから、被告車Bの動静に十分注意し、適宜減速するなどして本件事故を回避することが可能であった。しかし、漫然と本件道路に進入しているから、全く過失がないとはいえないと判断した。
その上で、名古屋地裁は、このように原告Aにも過失が認められるが、しかしその過失の程度は被告に比べて軽微であったと判定し、結局、原告Aに10%、被告Bに90%の過失を認めた。
思うに、この名古屋地裁の判決は妥当なものといえる。原告Aの「自分には過失はない」という主張も、その気持ちは分かるが、原告Aは、交差点の手前で、明確に被告車Bが一時停止をしていることを知っていたのであるから、やはり、判決のいうように僅かの落度は免れないと考えられる。
実は、この優先道路10%、非優先道路90%という数字は、弁護士などの実務家が頻繁に使用する「別冊判例タイムズ」に掲載されている基本的過失割合と同じである。私の経験に照らしても、別冊判例タイムズに掲載されている事故類型についていえば、余程の特別事情がない限り、そこに書かれた基本的過失割合に従って、実際の過失割合の認定が行われることが多い。
今回、私は、現在、上記の事故類型とよく似た類型(国道を走行する原告車と側道から出てきた被告車の衝突事故)を扱った裁判の代理人(原告車側)をたまたま務めている。その事故で、被告の代理人弁護士は、何を勘違いしているのかはよく分からないが、原告車40%、被告車60%という過失割合を主張している。もちろん、被告がそのように主張することは、原則として訴訟上の権利であり、違法ではない。しかし、主張の度が過ぎると、裁判所によって違法の評価を受け、慰謝料が増額されることになる。この場合、実務上そのような事例は珍しいので、結果、判例雑誌に掲載され(判例時報2065号101頁)、いつまでも記録に残る危険がある。
新聞報道によれば、岐阜県の美濃加茂市長であった藤井浩人氏は、最高裁の上告棄却決定を受けて、18日、異議の申立てを最高裁に行ったとの報道がある。
藤井氏は、名古屋地裁で事前収賄の起訴事実に無罪判決を勝ち取った。しかし、名古屋高裁では逆転有罪となり、最高裁に上告したものの、11日に上告が棄却され、有罪が確定した。
これに対し、藤井氏は、最高裁に対し異議の申立てを行ったのであるが、ここまでは普通の手法といえよう。しかし、19日の新聞報道によれば、仮に異議申立が退けられ、さらに再審請求も認められなかった場合は、民事訴訟を提起し、虚偽の供述を行った業者の男性に対し、「男性の虚偽の供述のために、刑事裁判で有罪が確定し、市長の身分を失ったことに対する損害賠償訴訟を起こす予定」との報道を聞き、私は疑問に感じた。
今回の事件に関し、私は新聞報道に書かれたこと以上の事実を知るわけでもないから、本当に藤井氏が無実なのか、あるいは有罪とした名古屋高裁及び最高裁の判断が正しいのかの点は不明である。
しかし、最高裁の決定が出る前の時点、つまり名古屋高裁において有罪の判決が出た直後の時点で、藤井氏の弁護人である郷原弁護士が、非常に自信満々の態度であったことが気にかかる。何か、名古屋高裁の裁判官は全く真実が分かっていない(有罪ではないことは、誰の目にも明白だ)といわんばかりの説明がされたことには、やや違和感があった。ある意味、有罪判決を下した3人の裁判官を批判したような様子がうかがえたのである(ただし、この点は私個人の印象にすぎず、そのような事実があったという意味ではない。)。
果たして、一刑事弁護人が、そこまで言い切ってもよい事件であったのかどうか、という点には疑問が残る。より慎重な姿勢が望まれたのではないか、と思うのである。
今回、藤井氏は、将来、贈賄側の業者の男性を民事事件で訴えることがあり得るという。
しかし、これは疑問である。確かに、民事訴訟として成立することには疑いがないが、しかし、その訴えが裁判所で認められる可能性があるかと問われれば、非常に厳しいというべきだからである。贈賄側の男性は、賄賂を藤井氏に送ったということで有罪となった。かたや賄賂を貰った側の藤井氏も、今回の裁判で有罪となった。したがって、司法の判断は、贈賄側も収賄側もいずれも有罪である、という判断で固まったのである。そのような状況下、藤井氏が、業者の男性に対し、「賄賂を贈ったという嘘の証言(供述)で、自分は市長を辞めることになった。これは、民事上の不法行為に当たるから、損害の賠償を求める。」と民事事件で訴えても、刑事事件の確定判決は、藤井氏は賄賂を貰ったということで固まっているのであるから、「嘘の証言(供述)はけしからん。一体どうしてくれる。」と息巻いても、そのような主張が民事裁判所で認容されるとは思えないのである。
藤井氏は、将来は、政治家の世界に戻りたいとの意向を持っているようである。であれば、今回の刑事裁判の経験を通じて、何が失敗原因であったのかを反省することに時間を費やした方が、時間の使い方としては有意義であると考える。
藤井氏は市長に当選する前は市議会議員であり、その前は、地元で学習塾を開いていたと聞く。今回の容疑は、市議会議員時代に発生したことであり、当時、藤井氏の社会経験不足に付け込まれた事件であったといえよう。その意味で、「脇が甘かった」ということである。
政治家の周辺には、得体のしれない輩が次々と寄ってくると聞く。政治に関わりを持つということは、ある意味、危険が伴うということであろう。十分に気を付けたいものである。

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.