
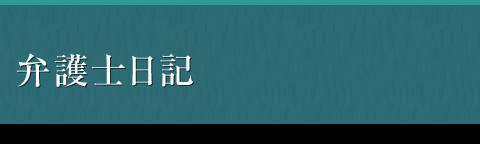
JR岐阜駅を出て北の方角に向けて真っすぐ1キロメートルを歩くと、演歌歌手である美川憲一の「柳ケ瀬ブルース」で知られた柳ケ瀬がある。この地は、今から半世紀以上も前の古い時代には多くの買物客が訪れ商店街は大いに賑わっていた。しかし、その柳ケ瀬は、その後、じわじわと衰退の歩みを始めた。
柳ケ瀬は、私の自宅から直線距離で1キロ以内の距離にあるため、これまで主に岐阜高島屋の食品売場や大型書店を利用するため、月に数回は訪れていた。しかし、本年7月末をもって県内唯一の百貨店である岐阜高島屋も閉店し、柳ケ瀬の衰退に一層拍車がかかると予想される。
折しも、2024年7月13日付けの岐阜新聞3面に「移転や撤退、店舗の減少傾向続く」という見出しの記事が掲載されていた。その記事によれば、「岐阜市の中心市街地の小売店舗数は、減少傾向が続いている」とあり、続けて「県の(中略)実態調査によると、中心市街地の商店街1階部分の店舗数は、2007年度の866店から、2023年度は414店と半数以下に減った」、「柳ケ瀬商店街でも、(中略)2007年度の454店から、2023年度には229店とほぼ半減した」とある。
このように岐阜市中心街においては、最近の16年間で商店の店舗数が半減したという驚くべき客観的データが出ている。このままの状態が継続すると、今後、16年間で、今ある店舗はさらに半減するという予測もあり得る(ただし、統計学的には減少速度は現在よりもやや緩和すると見込まれる)。
このように商店の店舗数が激減する原因として、➀人口減少傾向の影響、➁郊外に広い駐車場を完備した大型量販店やスーパーマーケットが整備されたこと、➂日本経済の低迷から来る市民の経済的余裕のなさ、などの要因があげられよう。
ここで、岐阜柳ケ瀬の今後について予想する。柳ケ瀬は、大きく、西柳ケ瀬と東柳ケ瀬に分けられる。二つのうち中心は東柳ケ瀬である。嘘だと思うなら平日の昼間に来ていただくと納得できると思うが、西柳ケ瀬は、ほぼゴーストタウン化している。怪しげな店舗が立ち並ぶ道路を歩いている人はまばらである。また、この点は東柳ケ瀬にも言えることであるが、アーケードが老朽化しており、非常に陰気臭い。運気が吸い取られる感じがする。正直言って、特別の用事がない限り決して近寄りたくない街である(ただし、この点は、あくまで私の個人的感想にすぎない)。
一方、東柳ケ瀬の方は、これまでは岐阜高島屋もあり、また、地域には大型高層マンションもあって、雰囲気は西柳ケ瀬よりは良い(少なくとも、警戒感を覚えることなく歩くことはできる)。しかし、何か特別のイベントが開催されていない限り、普段から多くの買物客が歩いているとは言い難い。明らかに衰退している。
最後に、今後、東柳ケ瀬について状況を改善する方策があるのか否かを検討する。
結論を先に言えば、「ない」ということである。一時代前のような商店街として賑わいを回復することはあり得ないと考える。理由は細かく言わないが、一言で表せば、時代の大きな流れ(変化)に逆らうことはできないということである。一体誰が東柳ケ瀬でわざわざ買い物をしようという気になるのか?根拠の薄い希望的観測を止めて、厳然たる事実を正面から捉えれば、誰にでも分かる結論であろう。
そこで、今後の在り方として、第1に、東柳ケ瀬の区画(南北300m、東西200mの長方形の区画)を再開発して、基本的に全面的に緑地化する。札幌市の大通公園のような爽やかなイメージの場所とする。
第2に、岐阜市の市民(約40万人)のうち、非常に多くの人数が、日々、名古屋の企業や学校に通勤・通学している事実があることを踏まえ、JR岐阜駅から北の方向に向かって一度に多くの人数を運べる公共交通機関を整備する。岐阜市には何も有力な産業がないのであるから、今後は、名古屋市のベッドタウンとして生きるほかない。
ここでは具体的にはモノレールが想定される。JR岐阜駅を出たモノレールは、北の方角に向け、「柳ケ瀬駅」、「岐阜市役所駅」、「本町駅」を経由して、終点の「岐阜公園駅」(または「金華山駅」)まで到達する。そして、岐阜公園駅(または金華山駅)の付近には大規模な駐車場と建物を整備し、県外から来る観光客の購買需要に対処するため、市内からやる気のある土産物業者・飲食店業者を多数誘致する(誘致に応じた業者に対しては補助金も出す)。
このように、岐阜市中心部を名古屋方面への通勤・通学に好都合な場所とするために、現在のような露天駐車場だけが年々増加する、衰退しつつある街を活用するという計画である。
この計画が実現すれば、岐阜市が今よりも活性化することを十分に見込める。柴橋正直市長には、在任中に是非ご検討いただきたいものである。

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.