
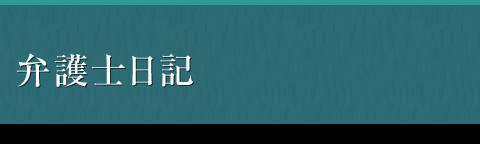
私が住む岐阜市内には、岐阜高島屋という百貨店があり、本年7月末をもって閉店する。つまり営業を無期限で停止すると聞く。地元の人であれば誰でも知っていることであるが、この百貨店は、岐阜市の中心部の中でも特に中心部に位置する。隣接して市内で一番高いと言われるマンションが建っている。付近の地価は、おそらく岐阜県内でも最高ランクに位置するはずである(ただし、正確にはJR岐阜駅前の地価が一番高いとされている)。
ところが、この百貨店が今年の夏に無くなるのである。私個人は、この百貨店が自宅から徒歩10分以内の至近距離にあるため、1階と地下にある食品売場をしばしば利用していた。また、9階にある書店(大垣書店)もときどき利用していた。しかし、それ以外のフロアーは全く利用したことがない(例外として、数年前に傘と革靴を買ったことがある程度である)。通常、店内はお客の姿が余りなく、いつも閑散としていた。活気というものが全く感じられなかった。当然であるが、幹部従業員の「顧客第1の精神」は希薄であったと感じざるを得ない。したがって、閉店というニュースを聞いても余り驚かなかった。
本日付けの岐阜新聞1面によれば、「ビル解体 進まぬ交渉」という見出しが載っていた。記事を読むと、賃貸借契約の終了に伴って、ビル解体の問題が発生するが、岐阜高島屋の親会社の高島屋が解体費用の負担を拒否しているということが分かった。一方、地主側の会社は、高島屋に対し、高島屋の自己負担によるビル解体を要求しているらしい。また、記事の3面を読むと、「高島屋が撤収時にビルを解体して更地にするという内容の取り決めの存在は両者とも認識している」、しかし、賃借人側の高島屋は、地主側の会社つまり賃貸人が、設備を更新しなかったことを問題視しているとも報道されている。また、新聞記事によれば、ビル解体の費用は最低でも10億円かかると試算されている。
この状況を法的に見るとどうなるか?土地賃貸借の基本については、民法に条文がある。原則として、原状回復義務が借地人にあり(民622条・591条1項)、高島屋の方で、ビルを解体する義務がある。しかし、民法の特別法である借地借家法13条によれば、借地権者は、賃貸人に対し、建物を時価で買い取るべきことを請求することができる(建物買取請求権)。民法と借地借家法は、一般法と特別法の関係にあるため、特別法である借地借家法が優先して適用される。しかも、当該条文は借地人を保護した強行規定とされている(借地借家法16条)。したがって、借地人にとって不利な内容の合意は無効となる。なお、本件契約が定期借地権である場合は、原則どおりとはならず、別途考察が必要となる。
では、仮に円満な交渉が頓挫して、双方で裁判に至った場合、どのような結末を迎えるか?
法的に、高島屋は、賃貸人側の会社に対し、営業を完全に終えるビルを「時価」で買い取れと請求することができる。問題は、設備が老朽化したビルなど、時価といってもゼロ円に近いものとなるのはないのか?という疑問が出てくる。したがって、仮に高島屋が建物買取請求権を行使しても、自分が受け取れるお金はゼロ円になる可能性が高い。しかし、高島屋はそれで十分満足であろう。今や利用価値を失い無用の長物と化した老朽ビルを自社の資産から切り離し(結果として、賃貸人の所有物とすることによって)、この地から無傷の状態で撤退することが可能となるからである。この場合、賃貸人側の会社は、所有者としての立場で、老朽化したビルをこのまま所有し続けるか(この場合、無駄な経費が年々累積することになる)、あるいは10億円を自己負担してビルを解体・更地化し、その後、当該土地を第三者へ売却あるいは共同開発することになろう。今後、いずれとなるかは不明である。これが、目下の私の見立てである。
(追記)
ここで留意すべき点は、法的解決を求める当事者が裁判所に訴えを起こしたからといって、必ずしも迅速に正当な判決が下る保障はないということである。新聞報道を手掛かりに調べたところ、2015年に発生した粗大ゴミ処理施設の火災をめぐる事件において岐阜地裁は、E環境プラントが岐阜市に求めていたゴミ処理報酬の支払い請求を棄却した。しかし、控訴されてその判決が名古屋高裁で変更された。名古屋高裁は、本年5月17日付けの判決で、岐阜市に対し1億2200万円の支払いを命じた。本年5月18日付けの岐阜新聞記事によれば、岐阜市の柴橋市長は「弁護団と判決内容を精査し、今後の対応を考えたい」と発言したという。当該コメントは無難な内容であるが、しかし、仮に最高裁に上告(または上告受理申立)したとしても、通常、最高裁において高裁の判決が覆ることはほとんどないため、今更、岐阜市が判決内容を精査し、上告(または上告受理申立)をしても、時間と税金の無駄遣いという結果となる可能性が極めて高い。そのような暇があるのあれば、当時の担当職員の事務処理が適切なものであったか否かを検証した方がよい。
また、岐阜県本巣市の真正中学のグラウンドの所有権をめぐって、岐阜地裁は、所有地を不法に占拠されたとして地元の男性が本巣市を訴えた事件において、男性の請求を棄却したが(原告敗訴)、控訴審である名古屋高裁は、男性の訴えを認める逆転勝訴判決を下した(ただし、判決日は不詳)。本年5月29日付けの岐阜新聞記事によれば、本巣市は上告を断念したという。本件では、男性による民法の取得時効の成否が争点とされたようであるが、名古屋高裁はこれを認めた。時効取得という論点は、民法の論点の中でも、基本中の基本と言い得る重要論点である。その初歩的解釈を間違えた岐阜地裁の裁判官の力量には一抹の不安が残る(裁判官のレベルが、昔と比べて低下しているのかもしれない)。
このように、岐阜地裁は、当事者の一方が権力を持った行政主体(市や県を指す)や有名企業ないし法人の場合、行政主体等に有利な判決を下す傾向があるように感じる(ただし、この点はあくまで私見にすぎず、事実を立証する統計資料があるわけではないことに留意されたい)。しかし、これはおかしい。裁判官は中立公正を旨とする仕事である以上、法と証拠に基づいて、常識に沿った正しい判決を出すよう努力すべきである。
本年4月に行われた衆議院東京15区の補欠選挙をめぐり、一部の心得違いをした者による他党候補者の街頭演説妨害行為について警視庁捜査2課は、本年5月13日、選挙妨害を行った政治団体に対する家宅捜索を行った。警察が家宅捜索を行った目的は明かにされていないが、上記政治団体の代表者または候補者に対し、公職選挙法違反(自由妨害罪)よる立件を視野に入れたものであると思われる。警察は本気であると睨んだ。テレビ報道による映像を見る限り、極めて悪質な妨害行為であり、違法なものであることは言うまでもない。実行者の行為は、世間の常識を逸脱した醜悪な行為に当たる。と同時に、違法行為である。このような違法な行為を今後繰り返させないためにも、警察には、この際、徹底した捜査を求めたい。
ところで、今回の事件に対し、産経新聞は、本年5月16日付けの社説で「国民の常識や良識に照らし悪質な行為が、合憲や適法であるはずがない。警視庁の捜査は妥当である」という見解を示した。この意見は、日本国民の多数の意見に合致したものと考える。実に妥当である。
今回、なぜこのような想定外の事件が起きたのか?想定外の事件が、何の前触れもなく突然起こるということもあろうが、大半は、その芽ないし原因が存在しているはずである。思い起こすと、令和元年に安倍元総理が、北海道で参議院議員選挙の応援街頭演説の最中に、一部の活動家が、街頭演説を妨害する意思で、安部氏に対し、ヤジを飛ばしたことがあり、それを北海道警察が摘発したニュースがあった。その後、摘発された2人の者は、北海道に対し損害賠償を求めた。その際、一審の札幌地裁は、北海道警察が2人を排除したことを違法と認定した。しかし、控訴審に当たる札幌高裁は、2人のうち男性については、警察の警告を無視して大声で連呼をする行為を止めなかったなどの理由で、警察の行為を適法と認め、札幌地裁の判決を取り消した。
札幌地裁の裁判官の考え方の浅薄さには呆れるほかない。条文や判例を記憶する能力は抜群であるが、物事を大局的に把握し、理解する能力は劣っていると判定せざるを得ない。この事件を担当した裁判官は、何を根拠に弁士に対しヤジを飛ばすことを適法と認定し、反面、それを規制した警察の行為を違法としたのか?ここ20年余りの長期間にわたって司法試験の合格者が激増し、合格者の平均的な資質が劣化したことが影響しているのであろうか?自分が司法試験に合格した当時は、合格率3パーセントと言われていた。それほど合格することが難しい試験であった。当時は、中国の科挙にも匹敵すると言われたものである。
しかし、昨今では、一定の能力があれば、努力次第で誰でも合格できる「ゆるゆるの試験」に成り下がってしまった。最近、首をかしげざるを得ないおかしな判決が出る頻度が増してきたように感じるが、司法試験が簡単になったこと(裁判官のレベルが低下したこと)が、ひょっとすると影響しているのかもしれない。
話を戻す。街頭演説は、それを聴きたいと思う者が現場に赴いて、候補者または応援弁士の演説を直接聴くためのものである。演説を聴きたくない者が、わざわざ現地に集結して演説を組織的に妨害するためのものではない。話を聴きたくない者は、街頭演説の現場に行くべきではなく、仮に現場に行った場合は、候補者または弁士の演説を妨害する意図で大声でヤジを飛ばすことは許されない。適法に実施されている他人の演説を「妨害する権利」など、そもそも存在しないのである。
そのような悪しき判例があったため、今回家宅捜索を受けた政治団体の代表も、とんでもない勘違いをしたのではなかろうか。このことから、今回のような、絶対にあってはならないことを引き起こさないためにも、選挙妨害行為に対する罰則を厳しくする必要がある。厳罰化が必須である。
ところが、例によって、5月16日付けの岐阜新聞社説は、「現行法での対処が妥当だ」などという間違った意見を掲載した。これはおかしい。岐阜新聞の掲げる根拠は、極めて薄弱である。岐阜新聞は、第1に「規制に抵触するのを恐れて各候補者の選挙活動が萎縮する恐れがある」と言う。しかし、全く理由になっていない。要点は、他党の候補者の街頭演説を妨害するような行為を慎めばよいだけのことであり、これまで大半の事例では、各候補とも良識を持って行動してきた。岐阜新聞のいう「選挙活動の萎縮」とは、一体何を言わんとしているのか不明である。第2に、「国家が選挙活動に過度に介入するようにならないかも心配だ」と言う。これも何を言いたいのか不明である。他党の候補者の街頭演説を妨害する行為をしてはならないというルールは、民主主義を守る上で重要な考え方であるところ、そのルールを破ろうとする横着者を取り締まろうとすることが、何故、国家による過度の干渉に当たると言えるのか?全く理解できない。第3に、「聴衆のヤジなどにまで規制が及び、憲法が保障する表現の自由が侵害される懸念もある」と言う。これも一種の不当な拡大解釈に当たる。今回のような右翼の街宣車顔負けの大音量で他党の候補者または弁士の演説を妨害する行為を規制することが、なぜ、表現の自由を侵害することになるのか?このような間違った姿勢では、結果として、今回の妨害者の悪質行為を容認するということにならないか?岐阜新聞の社説は、疑問だらけである。
連日のように栃木県那須町の河川敷で発見された焼死体の犯罪について報道が続く。
現時点で分かっているのは、報道によれば、6人の容疑者がこの凶悪事件に関与している可能性が高いということである。テレビ報道を見ていると、6人とも顔を下に向けて警察官に連行されてトボトボと歩いている。全員が下を向いているという姿を見る限り、やましいことをしたという心理が表出している。実に情けなく、また、見苦しい姿である。
6人のうち、一番悪質なのは、事件の首謀者である。ところで、6人のうち、関根容疑者は、殺害された宝島さん夫妻の娘の内縁の夫という関係にあったと聞く。内縁とは、外見上は普通の夫婦と見られるが、正式に婚姻届けを出していない状況を指す。殺害された宝島龍太郎さんの妻である幸子さんは、この関根という人間を嫌っていたという。当たり前の心理であろう。全身に入れ墨を入れているような人間は普通の人間ではなく、人間性に何らかの深刻な問題を抱えていることが多い。普通の世間の常識からすれば、まともな人間は、入れ墨などしない。入れ墨をしているということは、世間に対し、「自分は普通の人間ではない」というアピールのつもりなのであろう。実に下らないことである。南米に生息する毒カエルは、非常に派手な色をしているが、これと同じである。他人に警戒心を起こさせ、さらに威圧しようとする意図があると言い得る。最近、来日する外国人観光客の中に、入れ墨をしている不逞の輩をときどき見るが、そのようなたわけは入国させるべきではない。
さて、世の中で発生する犯罪の大半には動機がある。稀に「殺害する相手は誰でもよかった」などと白状する犯罪者もいるが、それはあくまで例外である。普通の犯罪が起きた場合、ある人物が殺害されることで利益を得ることになる人物が一番怪しまれることになる。
今回、報道によれば、関根容疑者が首謀者であるという印象が極めて強い。今後、犯行を裏付ける証拠が揃い、殺人罪で起訴された場合、判決では、宝島さんの事業を奪おうという動機が働いて今回の殺人行為を実行したと認定されることになるのではなかろうか。要するに、事情を知らない宝島さん夫妻を都内の空家に誘導し、そこで騙し討ちにする(殺害する)ことを通じ、会社の乗っ取りを計画したという事実が明らかとなろう。実に卑怯で非道な所業である。
警察には、今後も、真相を解明するために大いに頑張っていただきたい。
ただし、「推定無罪」という言葉がある。その言葉をどう理解するか、人によって違いがあろう。推定無罪とは、有罪判決が確定しない限り、国家がその者を犯罪者として法的に処遇してはならないということであり、法的な効果を離れた一般人の評価として、その者を犯罪者として評価することは(名誉毀損罪に当たらない限り)かまわない。なぜなら、それは内心の自由であり、また、通常の表現の自由に含まれると解されるからである。もちろん、表現の自由と言っても一定の制限があり、例えば、公職選挙において他党の候補者の演説を妨害する意図をもって、公衆の前で、大音量で他党の候補者を罵るような行為は最初から許されない(このような社会全体を舐め切った幼稚な行為は、厳しく取り締まる必要がある。即時、現行犯逮捕ができるよう、公職選挙法を改正する必要がある。この手の犯罪者には公民権の長期間停止が効果的である)。
以下は、今後、刑事裁判において6人の容疑者が全員有罪であると判断された場合の仮定の話である。今回の事件は、単なる私利私欲のために多数の者が共謀のうえで役割を分担し、結果、残虐な殺人事件を起こしたわけであるから、非常に悪質と言い得る。役割分担という構造は、暴力団の犯罪を思い起こさせる点があり、特に、厳しく罰する必要がある。
ここで問題は、死刑の適用である。私見は、被告人6人のうち、少なくとも首謀者に対しては死刑を言い渡すべきであると考える。2名の人間を残虐な方法で死亡させ、しかも、火をつけて焼くという行為は、とうてい普通の人間のやることではない。絶対に許されない。
ところが、弁護士の中には、「被告人の人権を守れ」と叫び、死刑は憲法違反であると声高に唱える一派が存在する。しかし、彼らのいう「被告人の人権」とは何を指すのか?他人を虐殺した凶悪犯について、死刑言渡しを回避することによってその命を助けることに何か意味があるのか?全く分からない。
今回のような凶悪事件については、被告人の正当な利益を考慮しても、やはり自分の命をもって罪を償うことが相当と考える。また、将来の「凶悪犯罪の新規発生を抑止すると」いう刑事政策的観点からも、裁判所の担当裁判官が、全うな判決を出すように期待したい。

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.