
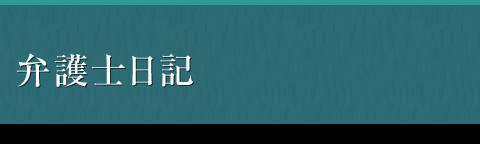
1 ある農地をAが所有し、その農地を株式会社である法人Bに賃貸している場合(ただし、3条許可あり)、他人Cは当該農地を買うことができるか?
結論を先に言えば、Cが非農業者の場合は買うことができないのは当然であるが、たとえ農業者であっても、原則として買うことはできない。その根拠は農地法3条2項に求められる。3条2項には、許可をするための要件が明記されており、最も重要な要件として2項1号がある。これは、農地を取得しようとする者(ただし世帯員を含む。以下同じ)が農地法3条許可申請をした際に、これから取得しようとする農地の全部について効率的に耕作事業を行うことができるものと認められることが許可要件となっているからである(効率的耕作要件)。ところが他人Bが賃借し、現にB自身が耕作中の農地は、Bのみが排他的に耕作する権利を持つため、第三者に当たるCは、当該農地を譲り受けても耕作することができない。そのため、Cは法3条許可を受けることはできない。
2 ただし、例外規定が置かれている。農地法施行令2条2項である。これはいわゆる法令に該当するから法的効力がある。同条2項イには上記と同じ効率的耕作要件が書かれている。この点は明確である。問題は、2項ロである。条文は、賃借権の「存続期間の満了その他の事由により」取得した農地を自分の耕作事業に供することが可能となった場合において、同じく効率的耕作要件を満たすことが必要とされる。仮にこの要件に適合すれば、3条許可を受けられる見込みが出てくる。
そのようなことが可能となるためには、本問の場合、法人Bにおいて間もなく契約期間の満了時期を迎える賃貸借の期間更新を希望しない、あるいは速やかに地主Aとの間で賃貸借を合意解約する意図があることが必要となる。つまり、法人Bにおいて今後の耕作事業を終了させることが客観的に明確になることが必要とされる。この点について、国の処理基準は、農地の権利を取得しようとする者について当該農地を耕作事業に供することが可能となる時期が明らかとなることを求めている(処理基準第3・3)。
さらに、国の処理基準は、許可申請者が農地の権利を取得してそれを耕作の事業に供することが可能となる時期が、許可申請の時点から1年以上先である場合は、許可をすることは不適当という見解を示すが(処理基準第3・3)、これはおかしい。上記政令の条文と矛盾することになると考えるからである。
仮に許可申請時から1年以内に耕作が可能となる状況が調っても、賃借人Bが許可申請時において依然として耕作を継続中の場合は、3条許可をすることはできないと解する。国の言う「1年」という期間に相当の理由ないし根拠があるとは思えず、思い付きの域を出ない不合理な数字と言うほかない。例えば、令和5年2月1日に許可申請が出たが、同年11月30日に従前の賃貸借が期間満了を迎えるというケースの場合、理屈としては、適法に更新拒絶を行えば、同年2月1日から「1年以内」にCによる耕作事業が可能となる。しかし、仮に同年3月1日に3条許可が出て、同日Cが農地の所有者兼賃貸人となったとしても、依然として11月30日まではBの賃借権が存続する以上、Cは、3月1日から11月30日までの9か月間は自ら耕作事業を行うことができない。このような説明のつかない事態を国(農水省の担当者)はどう考えているのであろうか?
3 一般論として、農地の賃貸人には、賃貸借契約上の主要な義務として、賃借人に当該農地を使用収益させる義務がある(民601条)。仮に賃貸目的物である農地を従前どおり賃借人Bが耕作しているにもかかわらず、新たに許可を受けて農地所有権を取得したCが、所有権に基づいて当該農地を耕作する事態が生じた場合、まさに賃貸人の義務違反行為(債務不履行)が生じる。よって、そのような違法状態の発生を容認しているとも受け取られかねない国(農水省の担当者)の法解釈は、到底妥当なものとは言えないのである。
ちなみに、民法によれば、農地の所有権がAからCに適法に譲渡された場合、農地の新所有者であるCは、上記のとおり、Aの賃貸人たる地位を引き継ぐことになる(民605条の2)。
以上のことから、許可申請時において、法人Bが賃貸人Aとの間の賃貸借を継続中である場合は、施行令2条2項に該当しないことになり、仮に譲渡人A、譲受人Cの3条許可申請が出されても、農業委員会としては許可をすることはできないと解する。
4 仮にCが法人Bの役員であった場合、Bは株式会社であるため、会社法上の問題が絡むことになり、事態は複雑化する。株式会社の役員とは、いわゆる中小企業の場合、通常は取締役を指すことになろう(会392条)。そして、株式会社と役員である取締役の関係は、委任契約となる(会330条)。そのことから、本問の役員=Cは、法人であるBに対し、善良なる管理者の注意義務を負う。Cは、その義務に背いて会社Bに損害を与えるような行動をすることはできない。
仮に法人Bの耕作事業の継続を認めつつ、同時にC個人の同一農地における耕作事業を認めるという申請内容であった場合、BとCの間に競業状態が生じ、Cは競業避止義務違反の責任を問われるおそれがある。競業について取締役会の承認があったとしても、農地法3条許可を受けた時点で、Cは、上記のとおり賃貸人たる地位を継承する。その場合、賃料の授受(賃料額の決定)をめぐって利益相反取引の問題が発生する。この場合も取締役会の承認を受ける必要があると解される。なお、取締役会における承認決議に際し、Cは利害関係人となるため、議決権を持たない。
以上のことから、法人の役員が、法人が借りている農地の所有権を取得することは想定外のことであり、また、一般的に推奨されることではないと考える。
(追記)
昨今、リスキリング(学び直し)という言葉が注目を集めている。農地法3条の許可権を持つ農業委員会で実務を担う一般職員も、常に最新の正しい法律知識を学んで、自分のものとする努力が求められる。その場合、自分で勉強しようとする姿勢も大切であるが、より迅速かつ正確に法的知識を身につけようとするのであれば、司法試験に合格している弁護士(ただし、農地法に関する一定レベルの知識は必要)の講義を聴くことが一番の早道であろう。同様に、農地に関わる税金問題を正しく理解しようとするのであれば専門家である税理士に、また、登記に関することであれば専門家である司法書士に相談するのが最も安全・確実と言える。

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.