
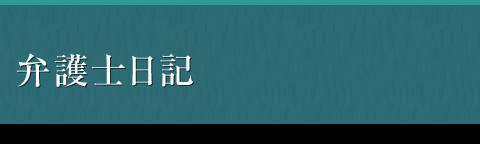
今回紹介させていただく事件とは、平成26年の晩秋に発生した交通事故が関係する事件である。
山田さん(仮名です。)は、当時、ある私学の4年生であった。深夜、アルバイト先から帰宅する途中で交通事故に遭った。加害者のYは、山田さんに高速で車を衝突させた後、救護義務を果たすことなく逃走した(いわゆるひき逃げ事件)。加害者Yは、間もなく警察に逮捕され刑事裁判において有罪判決を受けた。
ここで、過失相殺が問題となった。目撃者の話では、山田さんは、赤信号の表示があるにもかかわらず、横断歩道を渡り始めたため、今回の事故が起こったと供述し、刑事裁判でもその事実認定は覆らなかった。
当時、山田さんは、20歳代の若年年齢であり、私学の4年生であった。したがって、仮に重い後遺障害が残った場合、その賠償金は、かなりの高額に上ることが多い。ところが、被害者である山田さんは、今回の事故のような場合、賠償金の8割が減額されてしまう。いわゆる過失相殺である。分かりやすい例をあげると、仮に事故によって生じた賠償金が1億円とされても、被害者に8割の過失があると、その8割が減額されてしまうため、結局、2000万円の賠償金で我慢するほかなくなる。
ここで、被害者を救済する保険がある。それは人身傷害補償保険である(いわゆる人傷保険)。人身傷害補償保険に加入していれば、自分の過失分も補填してもらえる。ただし、約款上、計算方法は、あくまで保険会社の指定する方法で行うことになっているため、裁判所基準よりは相当に低額となることはやむを得ない。
上記の例で言えば、裁判所基準であれば1億円と算定されても、人身傷害補償保険では、通常は、7000万円~7500万円程度にまで低下すると推定される。
山田氏が当事務所に相談に来られたのは、事故から約1年経過した平成27年の秋のことであった。山田氏は、今回の事故によって高次脳機能障害を負った。問題は、その重さである。一口に高次脳機能障害と言っても、程度つまり障害等級によっては、賠償金額が極端に異なることになる(場合によっては、障害等級が僅かに異なるだけで数千万円の違いが発生することもあり得る)。
したがって、本人の代理人とされる弁護士の役割とは、これまでの知識と経験を活かし、自賠責保険によって不当に低い(軽い)障害等級が付けられないように活動することに尽きる。
さて、平成28年の症状固定を受けて、同年9月に、当職は代理人として後遺障害の等級認定のための申請を自賠責保険に対して行った。その結果、5級2号が認定された。
自賠責保険の等級認定を受けて、当職と山田氏はいろいろと検討した結果、いきなり裁判所に対し民事訴訟を提起するのではなく、山田氏が被保険者となっている人身傷害補償保険の請求を先行させようという結論に至った。
その結果、人身傷害保険会社が査定した金額は、7647万円とされたが、既払い金の1694万円を控除して、残額は5953万円となった。
しかし、今回、たまたま保険契約時に人身傷害補償保険の上限額を5000万円に抑えていたため、その金額(5000万円)が人身傷害補償保険会社からの支払額の限度となった。
仮に、契約時に1億円を限度額に設定しておれば、山田氏は5953万円まで補償を受けることができたわけである。その意味で、一般論として言えば、人身傷害補償保険の限度額は、保険料がやや割高になったとしても、1億円に設定することが望ましい。
山田氏は、このようにして人身傷害補償保険を受け取ってから、残額を訴訟によって加害者Yから支払ってもらう方針を立てた。損害賠償請求訴訟は、平成29年の秋にN地裁に対して提訴したが、今年の5月になってから裁判官から和解案が提示された。
私としては、「何だ、これは?」というような極めておかしな査定案であった。一方、加害者Yが契約していた損保会社の代理人の方からは、喜々として(ただし、この点は推測にとどまる。)和解案を受諾する旨の連絡が早々とあった。
他方、私は、和解案を拒否した場合のシミュレーション(計算式)を作成して、判決を希望した方が、受取額が大幅に増加するとの見通しを立てた。
しかし、依頼者である山田氏の希望を最大限優先して、和解に応じることとした。苦渋の選択であった。その後、本年6月になって、加害者Yが契約していた損保会社から、734万円の送金があり、これによって本事件は完全に解決するに至った。

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.