
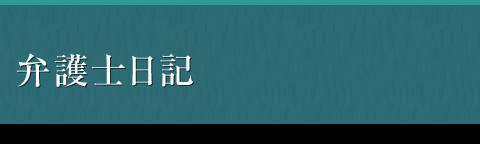
昨日、つまり2020年6月30日、最高裁は、いわゆるふるさと納税訴訟について、国を勝たせた大阪高裁判決を破棄し、泉佐野市の逆転勝訴判決を言い渡した。本日の朝刊各紙に判決の要旨が掲載されていたので、私なりに法的な分析を行った。ただし、手元にある資料は、新聞紙面だけであり、詳細まですべて正確に把握しているわけではないので、あくまで現時点における「簡易分析」にとどまる。
新聞紙を読んで、まず感じたことは、事実関係がよく分からないという点であった。しかし、新聞各紙を比較して読むことで、事実関係がある程度つかめた。次に思ったことは、判決を報道している記者が行政法の専門知識を欠いているためか、ポイントがズレているという点であった。
どの分野でも言えることであるが、専門家には、何がポイントかが分かっているので、そのポイントを押さえた的確な解説ができる。一方、聞きかじり程度の知識しかない場合は、どこが重要かが分かっていないため、焦点がボケた解説となる。仮に大学の法学部の教授であっても、行政法の専門家でなければ、的を得た解説はできないのである(そのことは、弁護士にも当てはまる)。
さて、判決要旨の分析に入る前に、事実関係を整理しておく。2019年(平成31年)3月に地方税法改正案が可決、成立した。改正法には、「返礼品が、寄付額の30パーセント以下で、しかも地場産品に限る」と定められた。いわゆる新制度に移行することになった。
同年4月、総務大臣は、改正法に基づいて、募集適正基準を定めた告示を出した。ところが、その告示には、2018年11月から、地方自治体が指定の申出書を国に提出するまでの期間内においても新制度の内容に合致している自治体のみが、新制度に参加することができるとの規定があった。
同月、泉佐野市は、新制度に参加したい旨の申出を行った。しかし、国は、同年5月、それを認めなかった。つまり、不指定とした(これは行政処分であると解される)。
同年6月、新制度が施行された。これに対し、泉佐野市は、国の決定は違法であるとしてその取消しを裁判所に求めた。その後、大阪高裁は泉佐野市の訴えを棄却した。
しかし、最高裁は、昨日、泉佐野市の訴えを認め、勝訴させた。後日、最終審である最高裁の判決が確定することによって、形成力が生じ、国の不指定処分は、最初から効力を失うことになる。つまり、最初から不指定処分はなかったことになる。また、国は判決の趣旨に従い、処分を行うことをしなければならなくなる。つまり、指定処分をすることになる。
では、最高裁判決の法的分析に入る。最高裁が、今回の国の不指定処分を違法として取り消した理由は何か?次の点があげられよう。
2019年3月に改正法が成立し、同年6月に施行された。一般に法律というものは、昔から「事後法の禁止」という原則があるとおり、法の遡及適用は原則的にできないことになっている。したがって、その原則に従う限り、2019年6月(なお、3月という考え方もあろう)より前に生じた事実は、新制度の参加者を選別する際に、考慮してはならない。
ところが、国は、上記募集適正基準を定め、新制度が施行された2019年6月よりも前の2018年11月から、参加申出時点まで、「寄付額の30パーセント以下の地場産品」という基準を満たすことを地方自治体に求めた。つまり、法の遡及適用をしようとした。
しかし、最高裁は、そのような募集適正基準は、改正された地方税法の趣旨を逸脱したものであり、違法で無効とした。有体に言えば、国つまり総務省が法律による行政の原則を踏み外し、「暴走」したということである。ここが重要ポイントである。
そして、募集適正基準は告示という形式をとっている。一般論として、告示には、法規命令の性質を持つものと、行政規則の性質を持つにすぎないものがある(塩野宏「行政法Ⅰ」112頁)。仮に今回の募集適正基準が法規命令であれば、法的拘束力がある。
ところで、最高裁判決は、今回の告示は、自治体に対する国の関与に当たる指定の基準を定めていると解釈しており、その意味からすれば、今回の告示は、法規命令に当たると考えられる。すると、「委任立法の限界」という有名な行政法上の論点に到達する。
今回の場合、地方税法の委任を受けて制定された募集適正基準のうち上記の箇所については、委任の趣旨を逸脱している(基準が暴走している)と判断されたため、違法無効とされ、違法無効の告示に基づく不指定処分も当然に違法無効とされたものと考える(なお、仮に改正地方税法に明文で委任立法を認めた条文がない場合であっても、結論に違いはない)。
なお、蛇足であるが、改正地方税法の条文を起案した総務官僚が、例えば、条文の中に「寄付額の30パーセント以下、地場産品に限るという要件を審査するに当たっては、過去の状況も総合的に考慮することができる」と書いた場合は、最高裁の判決が違っていた可能性がある。ただし、この場合は、事後法の禁止に抵触するという批判も出てこよう。
いずれにしても、今回の判決によって、霞が関の官庁の中でもそれなりの立場にある総務省の評価は著しく落ちたと言えよう。今回の判決は、一つの重要判例として長く歴史に刻まれることになろう。

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.