
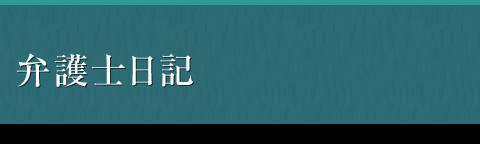
被害者側に立って交通事故の訴訟をしていると、訴訟の途中で、加害者側の方から、医師意見書というものが出されることがしばしばある。
医師意見書とは、裁判を起こされている加害者つまり損保会社の依頼を受けた医師が、損保会社のために意見書を書くものである。その内容とは、事故被害者の傷病について、同人にとって不利になる意見がほとんどである。
具体的に言えば、例えば、事故被害者Aさんが、ある病院に半年間通院して症状固定したとする。事故の被害者としたら、病院の主治医Bから、「通院をして治療に努めてください」と言われたからこそ、通院をするわけである。何も、趣味で通院をしているわけではない。
ところが、医師意見書を見ると、「そのような通院は不要であって、せいぜい2週間程度の通院で十分である」などという、患者からすれば、驚くような意見が書き連ねてあるのである。
このような医師意見書には、問題点がいくつかある。
第1に、医師意見書という名前に相応しい内容が伴っているか、という問題点がある。
医師意見書を書いている医師は、訴訟の実質的被告となっている損保会社(例えばCホールディングス)の子会社(例えばDメディカルサービス)に所属する医師であることが多い。その医師は、D社の社員として、日本全国の損保会社の支社から依頼された事案について、日常業務の一環として、来る日も来る日も、意見書を書いているのである。
つまり、その医師が所属する子会社(D)から見れば、訴訟の実質的被告となっている親会社(C)のために意見書を作成するということである。したがって、その医師は、立場上、親会社に不利になるような意見書を書くはずがないのである。極めて偏波な内容の意見書とならざるを得ないのである。
第2に、その医師意見書を書いている医師は、事故被害者である原告を診たことは一度たりともない。患者を一度も診ないまま、単に、裁判所に提出された、診断書、診療報酬明細書、看護記録等を見て、あれこれ勝手なコメントを書いているにすぎないのである。患者を診たことがない医師が、裁判所に提出する目的で、間違った内容の意見書を作成することは、医師の本来の在り方からみて疑問が多い。
第3に、これが一番問題であるが、これらの医師は、医師の本来の領分を離れて、弁護士でなければ行ってはいけないような領域に首を突っ込むということがある。これを、「非弁行為」と呼ぶ(弁護士法72条)。非弁行為を犯すと、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる(同77条)。
例えば、原告である被害者は、自賠責保険で後遺障害の等級認定を受けているにもかかわらず、医師意見書の中で、「本件は非該当であると考える」とか「非該当であるから後遺障害逸失利益は生じないと判断する」などの意見は、非弁行為に該当する可能性が高い。
医師が、原告の受けた傷病について、傷病名とか標準的治療法について意見を述べたりすることは全く構わないが、後遺障害の有無及びその程度にまで口を差し挟むことは私見によれば、許されないのである。
なぜなら、後遺障害の程度の判断は、治療を終了(又は中止)した時点における心身の状況が基礎となって行われるのであるが、医師が口出しできるのは、その時点の患者の心身の状況についてだけだからである(事実問題)。
例えば、「四肢の機能は全廃状態にあると判断します」と記載された主治医の診断書に対し、損保会社の子会社に属する医師が、その意見書で「四肢の機能が全廃状態にあるとは言えません」と疑問を呈する意見書を作成することは構わないが、「よって、障害等級は、5級2号に該当します」と意見書に記載することは許されない。
その時点における患者の心身の状況を基礎として、障害等級に該当するか、仮に該当した場合に何級何号に当たるかという判断は、純然たる法的判断である(法律問題)。
したがって、医師が、医師意見書の中で、受傷者である原告について後遺障害の有無及び等級に言及することは、弁護士にのみ認められた法的問題の「鑑定」を行うものと解釈することができる。非弁行為に当たる可能性が高いから、本来は行ってはいけないのである。
そのことに全く気付いていない医師が、現実に見受けられる。そのような姿勢は、早急に改められるべきである。
以上

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.