
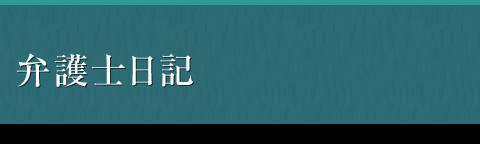
令和3年2月20日付けの産経新聞によれば、内閣府が行った最新の調査で、今後の日韓関係の発展が重要だと思わない、あるいはあまり重要だと思わないという回答が日本国民の40パーセントに達したとの世論調査結果が出た。また、同じく、日韓関係が良好だと思わない、あるいはあまり思わないという結果は82パーセントであった。
私の持論は、我が国は、今後、韓国との交流を中止せよというものである。仮にいきなり中止することが難しい場合は、できる限りのスピード感をもって交流を縮小する方向にもってゆくべきである。
理由をあげればきりがないので、ここでは、3つの理由をあげる。
第1に、戦後、韓国は、歴史的事実を歪曲し、日本を攻撃してきた事実をあげることができる。歴史的事実の歪曲の最たるものは、慰安婦問題の創作である。慰安婦問題については、最近、ハーバード大学のJ・マーク・ラムザイヤー教授が学術論文を発表している。ラムザイヤー教授によれば、慰安婦とは、韓国人や一部の反日的日本人が唱える「性奴隷」とは似ても似つかぬ存在であった。慰安婦とは、有体にいえば、売春婦そのものであった。
令和2年1月31日に産経新聞に掲載された記事によれば、ラムザイヤー教授は、「日本の本国政府や朝鮮総督府が女性に売春を強制したのではないし、日本軍が不正な募集業者に協力したのでもない。業者がもっぱら慰安婦募集を行っていたのですらない。問題は、数十年にわたり女性を売春宿で働くようにたぶらかしてきた朝鮮内の募集業者にあった。」と指摘する。つまり、慰安婦は、契約によって雇用された女性(ビジネスウーマン)にすぎない。
つまり、本人も納得ずくで働いていたのである。普通の一般労働者と基本は同じということである。また、これまでのところ、日本政府や日本軍が、朝鮮において慰安婦の募集に関係していたという証拠は一つも出ていない。にもかかわらず、韓国は、事実を歪曲し、あたかも日本政府ないし日本軍が強制的に女性を働かせたと嘘の宣伝を繰り返している。韓国人の大半も間違った情報に完全に洗脳されてしまっており、もはや修正不可能である。
また、令和3年2月21日の産経新聞によれば、韓国内では、ラムザイヤー教授に対する攻撃が始まり、米国のハーバード大学ロースクールの韓国人学生会が、ラムザイヤー教授に対する糾弾声明を出している。まさに狂気の沙汰という現象が起きている。思うに、韓国人という国民は非常に思い込みが激しい民族のようである。ちょうど、中世において、教会が天動説を採用していた時代に、地動説を唱える学者が出たところ、そのような考え方はありえないとして刑に処した事実と似ている。
歴史的な事実を歪曲する国民とは極力関わらない方が日本にとっては安全であり、無用のトラブルに巻き込まれないための有効な方法と考える。
第2に、以前にも述べたことであるが、韓国は、我が国の固有の領土である竹島を、李承晩政権以来長期間にわたって不法占拠している。分かりやすくいえば、竹島をわが国から盗んだ上、自分の領土であると大きな顔をしている。私は、このような泥棒根性にまみれた国とは、交流をすべきではないと確信する。仮に韓国が、竹島を日本に返還してきたときは、反省の情がうかがえるとして交流を考えてもよいが、泥棒国家である韓国が、竹島を日本に返還することは、天と地がひっくり返ってもあり得ない。絶対にない。
第3に、日本にとって韓国と交流することに利点がないことをあげることができる。一部の評論家は、韓国を西側陣営に繋ぎとめておくことは、日本の安全保障・防衛にとって重要であるという意見を吐くことが多い。しかし、これには疑問がある。なぜなら、上記の評論家の論理とは、我が国が、例えば、北朝鮮や中国と戦争状態に陥った際に、韓国は日本に味方するという大前提がある。しかし、これは幻想にすぎない。有事において、韓国はどちらに転ぶか分かったものではない。私の見立てでは、韓国は、むしろ北朝鮮や中国の側に付く可能性が高い。つまり、韓国は日本にとっては仮想敵国の一つということである。敵と交流することは、よほど警戒していないと、危険が伴う。
これらの理由に、なお一つ付け加えると、韓国という国は、日本が善意で行ったことについても、後になって何だかんだと非難を行い、日本を攻撃しようとする性癖がある。世間のトラブルメーカーと似ている。後になってから、言いがかりを付けられないためにも、交流の機会は、極力減らすのが上策ということである。
以上、我が国政府は、日本の国益を擁護するためには、いつでも韓国と交流を断つ、という強いメッセージを出す必要がある。ところが、現実は全く違う。韓国の顔色を窺おうとする卑屈な反日的政治家が野党のみならず、自民党にも多く存在する(マスメディアにおいても特にその傾向が強い)。いつまでたっても、太平洋戦争で連合国に負けた国というおかしな意識が残っているためであろう。いい加減、そのような過去の意識から脱局し、明治初頭にみられたような「富国強兵政策」を再び未来に向けて大胆に実行すべきである。

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.