
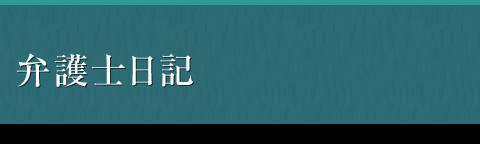
最近、テレビなどで急に「Chat GPT」の話題に触れることが多くなった。私は、スマホとかラインにはほとんど関心がなく、世間で流行しているツイッターとも無縁である。メールを使うこともまずない。
しかし、Chat GPTは、今後、弁護士業務に大きな影響を及ぼす可能性があると感じた。どういうことかと言えば、普通の弁護士が日常的に行っている法律相談に近いものがあると感じたからである。これまでの法律相談とは、例えば、一般市民が市役所などで開催される無料法律相談会に来て、担当の弁護士にいろいろと法律問題について尋ね、その質問に担当弁護士が口頭で回答するというのが通常だからである。
Chat GPTの場合も、質問をするとAIが口頭(ただし、現時点では文章か?)で答えてくれる。現在は、文章でしか答えが出ないようであるが、数年後には、音声でスムーズに答えてくれるようになるのではなかろうか?
そうすると、法律問題について解決案を聞きたいと考える一般市民は、AIに口頭で質問すれば、AIも口頭で答えてくれるようになる。この場合、AIは、あたかも弁護士のような機能を果たすことになる。しかも、勉強不足の弁護士よりも正確に答えてくれるようになるかもしれない。
そのようなことが当たり前になった場合、AIによる法律相談を自由にさせておいて良いのか、必ず議論が起こるであろう。なぜなら、一般の弁護士は、法律相談を契機として事件を受任し、その事件を解決することを理由に着手金を依頼者から貰い、また、事件をうまく解決することによって報酬金を得ることで事務所を経営しているからである。弁護士は公務員とは違って、一定の収入を得るには、必ず一定数を超える依頼を獲得する必要がある。そのための入り口が法律相談である。
仮にAIによる法律相談が一定の規制の下に認められるようになった場合、AIによる相談を受けた市民のうちの一定割合の者は、最初から訴訟を諦めることになる。つまり、その分だけ事件の依頼は確実に減少するということである。
この点を詳しく説明すると、正確な司法統計は別として、現実に原告つまり裁判を起こす側の当事者の勝訴率は、おおむね6割台と言われる。したがって、10件の裁判があれば、原告のうち6人は勝つことになるが、逆に、4人は負けることになる。その4人について、仮に最初から裁判を行うことを差し控えれば事件の総数は6件となる。もちろん、事件によっては最初から勝敗を度外視した訴訟もあるため(例えば、名誉毀損による損害賠償請求訴訟や騒音差し止め訴訟など)、必ず4件分減少することにはならないであろうが、減少することは不可避である。
ここで、「現在、弁護士に相談した場合であっても、10件中4件は、厳しいかもしれないという助言を得ているはずであるから、AIによる相談であっても特に差はないのではないのか」という反論があり得る。しかし、弁護士の場合、AIと違って事務所を維持する必要もあって、敗訴の可能性が高い事件であっても、「訴訟を起こすことは止めた方が良いです。仮に依頼があっても私は引き受けません」とは、言いにくいのではなかろうか?その点において「AI弁護士」と差があるのである。
このように、今後ますます弁護士を取り巻く経済的環境は厳しさを増すことになろう。40年前だったら、司法試験に合格すれば、即、中流以上の生活を送ることができる目途がついたと言えたが、今は違う。今後は、弁護士間の経済格差も深刻なものとなってゆくと予想される。
また、ひと昔前は、司法修習生を終えて初めて弁護士になった者はほぼ全員が他の弁護士に雇われ(これを「イソ弁」という)、スキルを身につけた上で、何年かした後に独立して自分個人の法律事務所を開設することが当たり前であった。
ところが、最近では、イソ弁がなかなか独立しないという話を聞く。そのため、経営者弁護士が、イソ弁の給料を長年にわたって負担せざるを得ず、これがかなり経済的に負担となっているとも聞く。独立志向が弱まっているということである。原因は、若手弁護士が独立して自分の事務所を立ち上げても、人件費、家賃などの負担が大きいため、イソ弁時代よりも困窮してしまうため、あえて独立しないということである(独身の男性または女性が、結婚せずに実家に長年にわたって居付く現象と似ている)。
このように、今後は、年収2000万円以上を毎年稼ぐことができる一部なの裕福な弁護士がいる一方で、一生イソ弁の身分で、年収500万円~1000万円程度で生活する弁護士が多くなるのではないかと予想する。ただし、一定規模以上の中堅・大型法律事務所では、当初はイソ弁として入所しても、能力次第ではパートナー弁護士(雇用する側の弁護士)に昇格し、そのまま業務を継続するという場合も多いように思える。

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.