
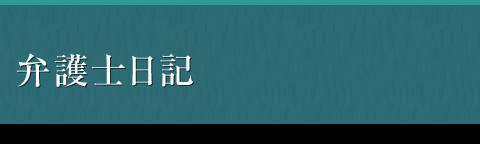
昨日、つまり本年2月20日に、名古屋市内において愛知県弁護士会が主催した講演会があった。講師は、元東京高等裁判所の部総括判事であった加藤新太郎先生である。加藤新太郎先生は、現在は退官されて東京で弁護士登録されておられ、某有名法律事務所に所属しておられるとのことであった。加藤新太郎先生は、私の大学の先輩であり、名古屋大学の法学部在学中に難関の司法試験に合格をされた超俊才である。しかし、その人柄は全く偉ぶったところがなく、むしろ庶民的な雰囲気を感じさせる人物である。
さて、昨日の演題は「民事立証・尋問技術」というものであった。加藤新太郎先生は、あらかじめ用意されたレジュメに従って、熱意をもって講義をされた。聞いている受講者(全員が弁護士)も、貴重なご経験をもとに話されている民事尋問技術に関する知識を一言も聞き洩らすまいと、全精神を集中して聴いているように感じた。
そして、主尋問についていえば、あらかじめ裁判所に提出する陳述書と矛盾しないような答えが法廷で出てくることが基本であると説かれた。私の経験でも、かなり以前のことであるが、依頼者(原告)が作成した陳述書と異なった供述を法廷で行った原告について、判決をみると、その点の指摘があり、このとき、「陳述書と矛盾した話をすると、かなりマイナスになる。気をつけなければならない」と感じた。
加藤新太郎先生は、主尋問が成功するか否かは、事前の準備をどれだけやったかにかかるといわれた。また、普通、陳述書は、弁護士が本人から聴き取って弁護士が内容を整理整頓して、その内容を本人に見せて確認をとってから裁判所に提出するべきものであると話をされた。愛知県弁護士会の会員の場合、愛知県弁護士会では、毎年、会員の弁護士に向けた、現役判事による実務的かつ有益な講演会などを数多く開催し、意欲のある弁護士つまり勉強熱心な弁護士ほど参加をしているので、会員全体の一般的能力が高い。
ところが、私の経験では、周辺の弁護士会に所属している弁護士の中には、名古屋基準に照らした場合、平均的レベルを下回る弁護士が目についた。
もちろん、その弁護士が所属する弁護士会の全体がそうであるというつもりは全くないし、また、そう推論する証拠もない。したがって、以下に記載するのは、私の個人的・主観的な経験談ないし感想にすぎない。その点を最初にお断りしておく。
たまたま偶然に私の相手となった弁護士は、平均的なレベルを下回る弁護士ばかりであった。では、なぜそういえるのか?それは、その弁護士が作成した書面の内容がしっかりしていないということが第1に挙げられる。私であれば、もっとしっかりと記載するのに、記載内容が希薄で、「果たしてどうしても勝ちたい意欲があるのか?」と疑われる内容の書面が多かったからある。
第2に、法律知識の面をみても、本当に法律をよく知っているのか?という疑問が湧くような記載しかなかったなど、おしなべて低レベルだったのである。
加藤新太郎先生は、講演の最後に、受講者からの質問を受け付けられた。若手の弁護士が、数名手を上げて、質問した。これに対し、加藤新太郎先生は丁寧に応答をされていた。最後の質問者はかなりのベテラン弁護士であった。
その弁護士の質問は、今回の講演は弁護士に向けた注意点を講義するというものであったが、では、裁判官には問題はないのか?つまり、近時の裁判官の資質に関する、ややきわどい質問であった。
これに対しても、加藤新太郎先生は、逃げることなく真摯に応答をされた。加藤新太郎先生は、退官前の6年間は、東京高裁で、裁判長として控訴事件を担当された経験をお持ちであった。東京高裁といえば、最優秀の裁判官が集まるところである。
その貴重なご経験によれば、次のようなことがいえるとのことであった。
一審判決のうち、全体の判決のうちの2割程度が控訴される。控訴されるのは、もちろん敗訴判決を受けた方が、判決の内容に不満を持つからである。控訴審の裁判官の眼から見た場合、半分近くは、判決の内容に問題がある。なぜ問題があるかを分析すると、つぎのように要約できる。
第1に、一審当時に争点整理が全くされていない事件や、争点整理がされていても不十分な事件には、問題が多い。
第2に、一審の裁判官において経験則がよく分かっていないため、判決に問題を生ずることがある。
第3に、担当裁判官が、一方当事者の主張に引きずられすぎてしまい、間違った結論に至っているものも少なからずある。
この話を聞いて、私はそのとおりだと思った。実は、私が関係する騒音公害訴訟がG地裁であったが、その判決は被害者の請求を棄却するという不当なものであった。騒音公害を出しているG市内の某病院は、長年にわたって騒音規制法に定める騒音基準を上回る騒音を日々出していたにもかかわらず、である。この不当判決に対し、原告は直ちに控訴し、N高裁で約11カ月後に和解が成立し、某病院も騒音量を低減するよう努めるとの意思を表明し、事件はひとまず解決したのである。私としては、熱意を持って紛争を円満に解決しようと努力をされたN高裁の裁判官には、敬意の念を持たざるを得ない。
一方、一審であるG地裁の裁判官が審理をしている時点で、双方に対し、適切に和解を勧告していたとしたら、もっと早く紛争が解決していたかもしれない。私は、G地裁の3人の裁判官が下した不当判決は今でも認めないし、これらの裁判官の姿勢には、依然として強い不信感を持っている。

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.