
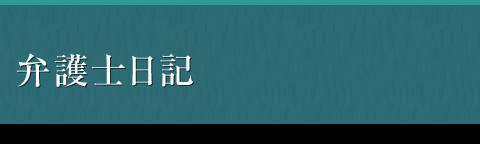
昨日は「竹島の日」であった。竹島については韓国による根拠のない不法占拠が続いている。韓国による日本領土の不法占拠の事実は、それ自体が、国家間の国際的紛争を生じさせる事実に該当する。
何事でも同じことであるが、法的紛争というものは、例えば交通事故のように全く予期せずに突発的に起こる場合もあるが、多くの場合は、長年にわたって継続した事実が根本原因となっている場合が多い。
例えば、国内の土地の境界線をめぐる問題は、ある日、急に生じるものではない。一方の土地所有者Aが、隣人Bの土地に食い込む形で塀を建て、Bの土地の占有を始め、そのようなおかしな状態が長年にわたって続いた結果、ようやく隣人Bが「Aが自分の土地に越境して塀を建てて使っている。これはおかしいではないか。」と声を上げる場合が典型例である。
その場合、国内であれば、Bが裁判所に駆け込み、民事訴訟を起こし、正しい境界線を決めてもらうことで紛争が解決する。Bが一方的に訴訟を起こした場合、仮にAがそれを無視して出廷しようとしない場合、普通は、Aにとって不利な内容の判決が出る。ただし、Aの不法占有期間が20年を超えると、本来の境界線(筆界)の問題とは別に、越境部分の土地の所有権が、取得時効によってAに生じるという厄介な問題が起こる可能性が高い。
本来であれば、このような事態になる前に、つまりAによる越境行為が始まった直後に、BはAに対し「塀をすぐに撤去しろ」と請求する必要があった。
ところで、国際紛争の場合、国家間の紛争は、国際司法裁判所(ICJ。インターナショナル コート オブ ジャスティス)が審理をして、判決を出して解決することになっている。
しかし、国内紛争と大きな違いがあり、強制管轄権が存在しないため、双方の国が合意して管轄権を認めるか(付託合意)あるいは一方の国が提訴したのに対し、相手国も応訴することで管轄権が生じる場合がある(応訴合意)。そのほかにも、あらかじめ将来生じる紛争についてICJに付託することを合意していることで(裁判条約)、管轄権が生じる場合がある(柳原ほか編「プラクティス国際法講義」369頁参照)。
日本が、勧告による竹島の不法占拠問題について平和的に決着を付けようとして、仮に国際司法裁判所に提訴した場合、韓国としては、強制管轄がないことを理由に、裁判所に出てこない可能性が非常に高い。裁判で負ける可能性が高いからである。敗訴することを恐れているのである。
では、なぜ韓国が敗訴するといえるのか?それは、以下の事実からである(年表については産経新聞2021年2月22日付け朝刊参照)。
➀ 日本は、明治38年に、政府が竹島を島根県に編入することを閣議決定した。日本政府が国家として正式に閣議決定した以上、明治38年以降、竹島は、法的に日本領になったということである。
ここで疑問が生じる。その時点で、韓国政府は、日本の決定に対し抗議をしなかったのか、という疑問である。韓国は、当時、日本に対し何ら抗議をしていない。ということは、当時、韓国政府は竹島が日本の固有の領土であることを認めていたということになる。
➁ 明治43年、日本による韓国併合が行われた。韓国は、韓国併合条約を日本と締結したということである。ここで次のような意見が韓国から出ている。上記の編入が行われた際、韓国は国力が弱かったので、日本に抗議することができなかった、と。しかし、これは理由にならない。国として抗議をすることは、何も武力を行使するような大事ではないから、容易にできたはずである、と。韓国流の解釈からは、太平洋戦争で日本が敗戦し、GHQの命令下で制定された日本国憲法など無効ということになる。
➂ 昭和27年1月、韓国は、一方的に「李承晩ライン」を設定し、日本領である竹島を李承晩ラインの内側に取り込んだ。つまり、事実上の占有を開始した。韓国は、泥棒行為を行った。また、日本漁船を違法に拿捕し始めた。
本来であれば、このような違法行為に対し、日本は実力を行使し、李承晩ラインを認めないという対応をする必要があった。しかし、敗戦後の国力不足の時代が災いし、できなかった。
➃ 昭和29年、韓国は、海洋警察隊を竹島に常駐させるようになった。
➄ 昭和40年、日韓基本条約が締結され、李承晩ラインは撤去された。しかし、竹島問題は棚上げされた。日本は、問題解決の好機をみすみす逃した。
日本外交の一番の弱点が、ここで表面化した。日本は、昔から懸案事項を先送りするという悪い文化があるということである。その精神とは、物凄い労力を払ってギリギリと論点を詰めて問題を合理的に解決するよりは、話し合いで解決できる事柄だけをすぐに解決し、難題については将来に委ねようという安易極まる精神である。難しい話は、すべて先送りしようという根性であり、世にいう「事なかれ主義」と共通する。いわば、責任放棄ということである。
本来であれば、日韓条約が締結される際を利用して、竹島は日本領であるという事実を韓国に文書で認めさせる必要があった。国家間の条約において「竹島は日本の領土である」と明記しておけば、少なくとも、今日のような韓国による竹島の全面的不法占拠はなかったのである(もっとも、韓国という国は国際合意を平気で破る信用のならない国であるから、書面化しておいても、その後、竹島に居座り続けたかもしれない。)。
以上のことから、我が国は、即座に国際司法裁判所に提訴すべきである。仮に日本が勝訴しても、韓国が不法占拠を改めない可能性が高いが、世界に対し、韓国は判決を無視する後進国であるというマイナス情報を発信することができる。これは、韓国を牽制するための一つの武器となる。仮に日本が敗訴した場合は、現状が維持されるだけのことであり、特に大きなマイナス面は生じない。
今後も韓国に対しては、他の国以上に大きな警戒心を払う必要がある。間違っても「友好親善」などという空虚な美辞麗句に惑わされてはいけない。日本の全てを「悪」とみなす、世界で唯一の反日国家である韓国(人)との融和は、未来永劫あり得ない。

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.